コンビニ店主は労働組合法の労働者か2~中央労働委員会命令~
セブンイレブン東大阪上小阪店の店主が,
24時間営業を辞めて,セブンイレブンの本部と対立していた問題で,
セブンイレブン本部は,店主に対して,
時短営業を理由とする契約解除をしないことを伝えたようです。

とりあえず,現状は時短営業が事実上追認されたのですが,
セブンイレブン本部は,24時間営業を維持する方針に
変わりはないようで,今後,この問題がどのように
進展していくのか見守っていきたいと思います。
さて,コンビニ店主の働き方がクローズアップされている中,
3月15日に中央労働委員会において注目すべき命令をくだしました。
先日,ブログで紹介した,コンビニ店主を
労働組合法の労働者としたセブンイレブンの
岡山県労働委員会の命令と,ファミリーマートの
東京都労働委員会の命令の判断を覆し,
コンビニ店主は,労働組合法上の労働者ではないと判断されたのです。

コンビニ店主にとっては,残念な逆転敗訴でした。
本日は,3月15日の中央労働委員会の命令について説明します。
労働組合法の労働者は,相手方との個別の交渉において
交渉力に格差が生じ,契約自由の原則を貫いたのでは
不当な結果が生じる場合に,労働組合を組織して
集団的な交渉によって保護が図れるべき者が含まれます。
そのため,労働基準法の労働者よりも,
保護される範囲が広いのです。
労働組合法の労働者に該当するかについては,
次の要素を総合考慮して判断されます。
1 基本的判断要素
①事業組織への組み入れ
②契約内容の一方的・定型的決定
③報酬の労務対価性
2 補充的判断要素
④業務の依頼に応ずべき関係
⑤広い意味での指揮監督下の労務提供・一定の時間的場所的拘束
3 消極的判断要素
⑥顕著な事業者性
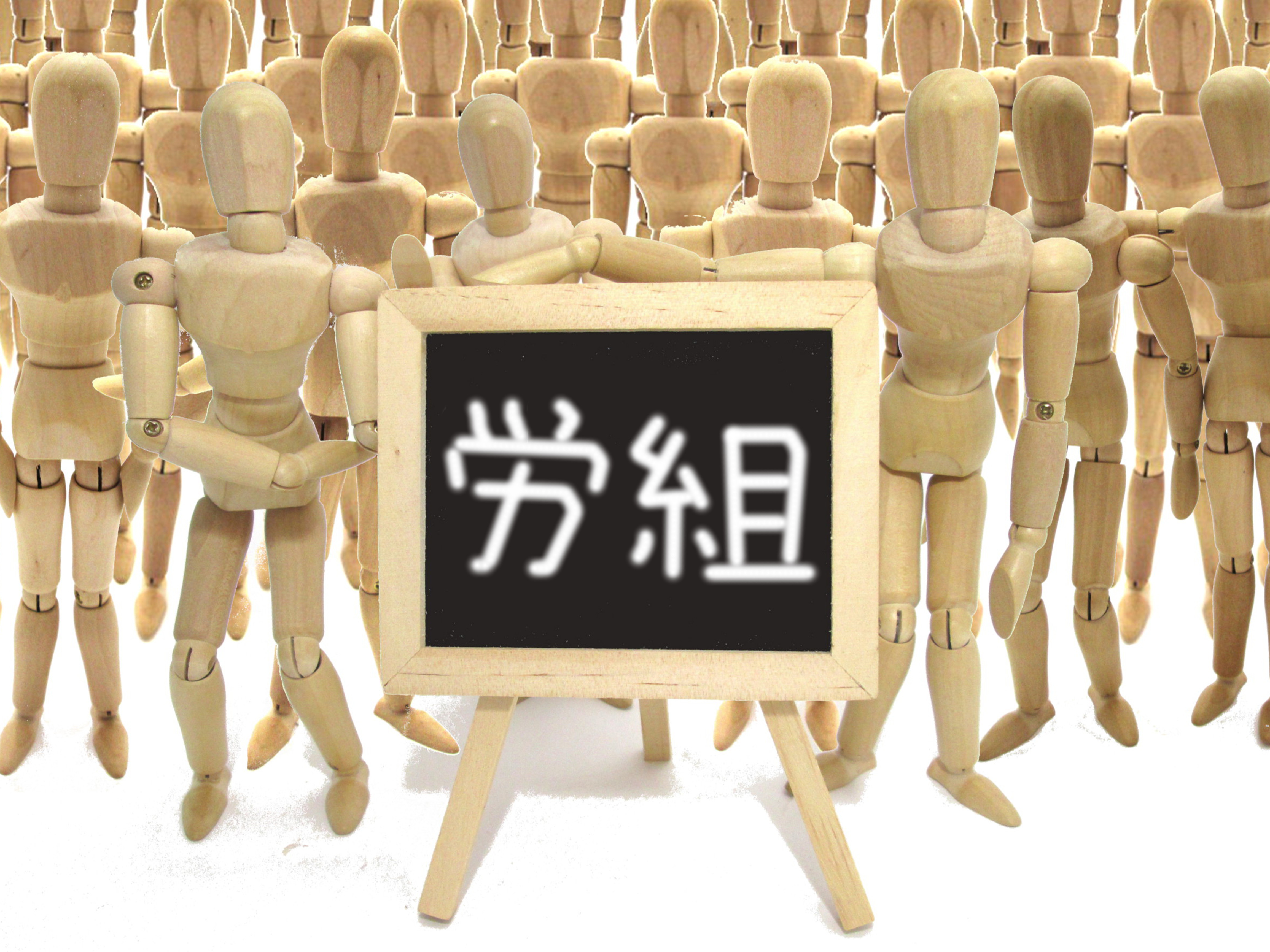
コンビニのフランチャイズ契約は,
本部が一方的定型的に定めており,
コンビニ店主が個別交渉で変更することは困難です(②)。
コンビニ店主は,本部から経営の助言・指導を受けて,
店舗において長時間働いています(⑤)。
そのため,都道府県労働委員会は,
コンビニ店主を労働組合法の労働者と認めたのでした。
しかし,中央労働委員会は,コンビニ店主は,
自ら資金調達をして事業の費用を負担し,
損失や利益の帰属主体として,
自らの判断で従業員の雇用や人事管理を行うことで
他人の労働力を活用し,自ら選択した場所で
コンビニの経営を行っているので,
経営者として相当の裁量を有する独立の小売事業者であり,
本部の労働力として組織に組み込まれていないと判断されました(①,⑥)。
フランチャイズ契約は,コンビニ店主の労働条件というよりは,
店舗経営という事業活動の態様について規定しており,
本部がその内容を一方的に決定していても,
労働組合法の労働者性を根拠付けることにはならず(②),
コンビニ店主が本部から受け取る金員については,
コンビニ店主の労務供給に対する報酬とはいえない(③),
と判断されました。
結論として,コンビニ店主は,
独立した小売事業者であって,
労働組合法の労働者に当たらず,
本部が,コンビニ店主が加盟する
コンビニ加盟店ユニオンからの
団体交渉申入に応じなかったとしても,
不当労働行為に当たらないと判断されたのです。

コンビニ店主は,コンビニの店舗を経営しているので,
「労働者」と捉えるのは多少違和感があるものの,
本部との間で,交渉力,資金,情報において,
圧倒的に格差があり,事実上長時間労働をしていることから,
コンビニ店主を保護すべき必要性があり,
現行法では,コンビニ店主を保護する仕組みは,
労働組合法以外にはないのです。
コンビニ店主個人では力がないのですが,
労働組合法の労働者と認められれば,
コンビニ店主が団体で交渉できて,本部は,
交渉に応じなければならず,対等に交渉でき,
本部に対して,自分達の要望を受け入れてもらえる
可能性がでてくるのです。
コンビニ店主の現状を見ると,
労働組合法の労働者として保護するか,
本部とコンビニ店主の法律関係を規律する
フランチャイズ法などを制定するか,
のどちらかが必要だと考えます。
コンビニ加盟店ユニオンは,
中央労働委員会の命令を不服として,
行政訴訟を提起するようですので,
裁判所において,コンビニ店主が労働組合法の労働者
として認められるのか,注目していきたいと思います。
本日もお読みいただきありがとうございます。




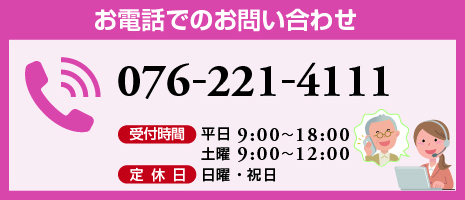
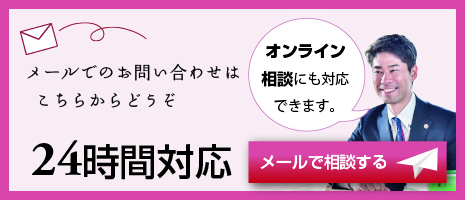

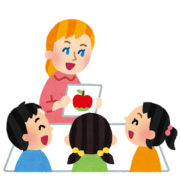


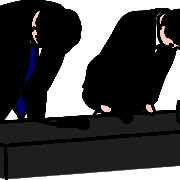









返信を残す
Want to join the discussion?Feel free to contribute!