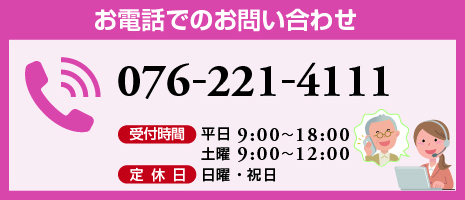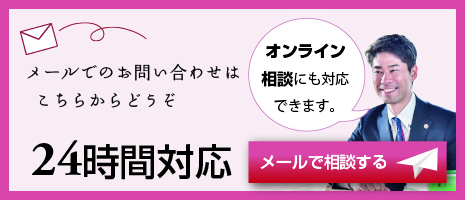相続事件
相続全般について
被相続人が死亡すると相続が開始します(民法882条)。遺産分割は、被相続人が死亡時に有していた財産(遺産)について、個々の相続財産の権利者を確定する手続きです。
遺産分割に先だって、遺言書の有無を確認しておく必要があります。
遺産分割は、大まかに言いますと、相続人の範囲を確定し、財産(遺産)の範囲を確定し、どのような割合で(具体的相続分)、どのように分けるか(分割方法)という手順で進めます。この過程には、遺産の評価や、特別受益、寄与分の確定も含まれます。
遺産分割については、遺産分割協議といって相続人間での話し合いが成立する場合もありますが、中には協議が調わない場合や、協議をすることができない場合もあります。そのような場合は、相続人は家庭裁判所に遺産の分割の請求をすることができます。
相続・遺産分割に関しては、このように事案に応じて検討すべきことが多くありますので、ご相談ください。
もちろん遺言書作成のご依頼も承っています。
遺言書
遺言にはいくつかの方式のものがありますが、ここでは最も一般的と思われる自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。
a)自筆証書遺言(民法968条)
遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自分で書き、押印して作成する方式の遺言です。誰にも知られずに簡単に遺言書を作成でき、費用もかからないという半面、方式不備で無効とされる危険性が高く、偽造・変造される危険性もあります。
b)公正証書遺言(民法969条)
遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する方式の遺言です。通常は公証人役場に遺言者が赴いて作成されることが多いですが、例えば、遺言者の健康状態等の事情から公証人役場に赴くことが困難な場合などは、公証人に遺言者のご自宅や入院先の病院等の場所に来てもらうこともあります。
公正証書による遺言のメリットは、次のとおりです。
- i 内容的に適正な遺言ができる。
- ii 遺言意思が確認できるから、無効などの主張がされる可能性が少ない。
- iii 公証人が原本を保管するので、破棄・隠匿されるおそれがない。また、相続人による検索が容易である。
- iv 家庭裁判所の検認※の手続が不要である。
- ※家庭裁判所による遺言書の検認とは、遺言の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の状態を確定し、その現状を明確にするものであり、後日の紛争に備えて、偽造・変造を防止し、遺言書の原状を保全する手続です。
遺言書の検認手続は、公正証書遺言以外のすべての遺言書に要求されています。
遺言の保管者は、相続開始を知った後に遅滞なく、相続開始地の家庭裁判所に遺言書検認の申立をしなければならないとされています(民法1004条1項)。
このような公正証書遺言のメリットから、弁護士とすれば、費用がかかる等の点はありますが、できれば公正証書遺言をおすすめします。
公正証書遺言作成の場合には、証人2名以上を立ち会わせることが必要ですが、ご依頼を受けた場合は、弁護士及び当事務所の事務員が公証人役場まで同行し証人として立ち会うことも可能です。
特別受益(民法903条)
共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けたりした者がいた場合に、相続に際して、この相続人が他の相続人と同じ相続分を受けるとすれば、不公平になります。そこで、民法は、共同相続人間の公平を図ることを目的に、特別な受益(贈与)を相続分の前渡しとみて、計算上贈与を相続財産に持戻して(加算して)相続分を算定します。
寄与分(民法904条の2)
共同相続人中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をした者があるときに、相続財産からその者の寄与分を控除して相続分を算定し、その算定された相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とすることをいいます。
遺留分制度(民法1028条以下)
遺留分制度とは、被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を一定の法定相続人に保障する制度です。
「遺留分」とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分(贈与・遺贈)に制限が加えられている持分的利益をいいます。
被相続人が贈与や遺贈を行ったため遺留分が侵害されたときに、受遺者や受贈者などに対して、その処分行為の効力を奪うことを遺留分の減殺といい、遺留分減殺を内容とする相続人の権利を遺留分減殺請求といいます。
「遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知った時から1年で、時効により消滅する。相続開始時から10年を経過すれば消滅する」(民法1042条)と規定されています。
遺留分に関しては、このように短い時効期間が定められていますし、法律的に難しい点がかなりあります。お早めにご相談ください。