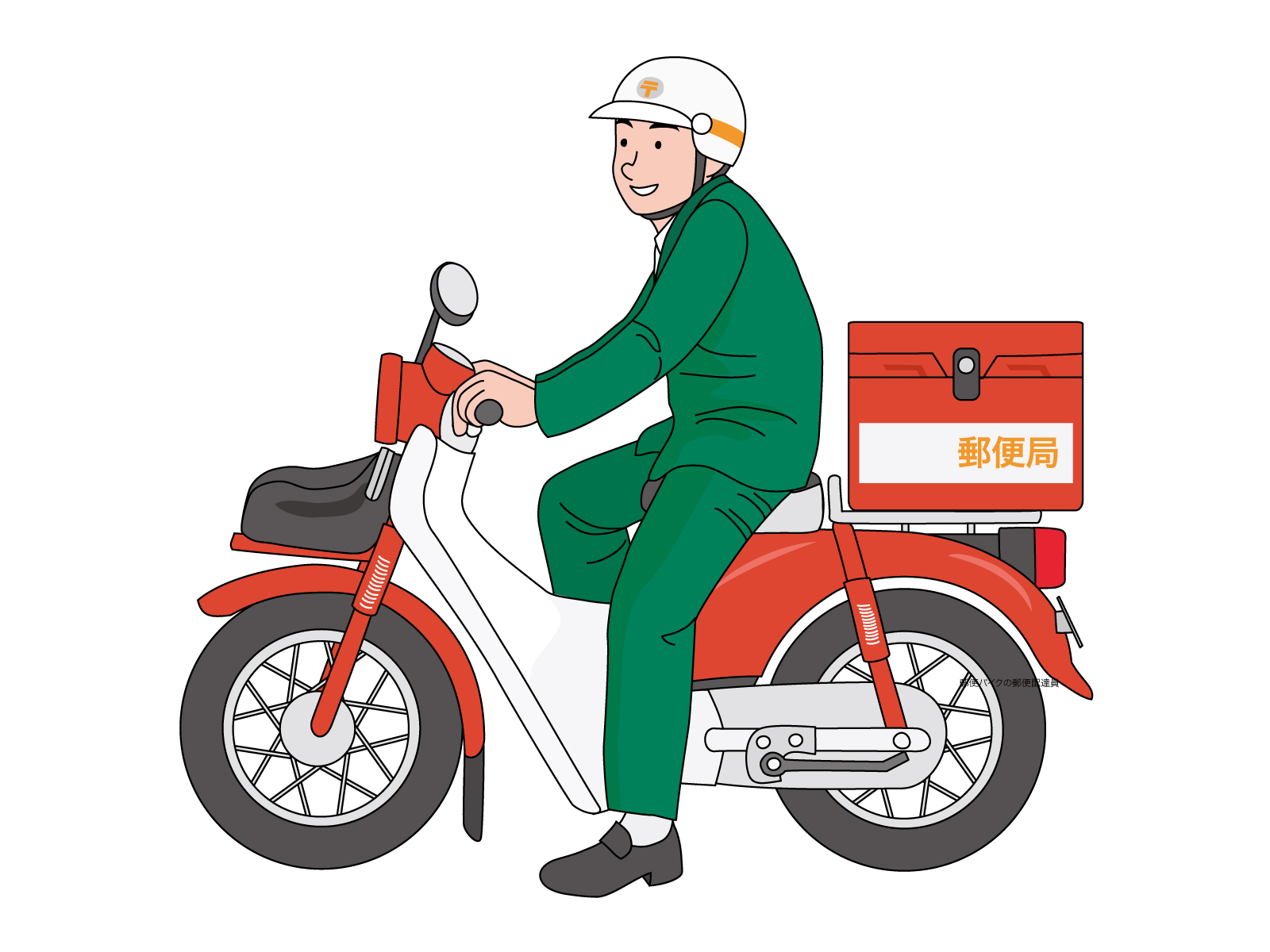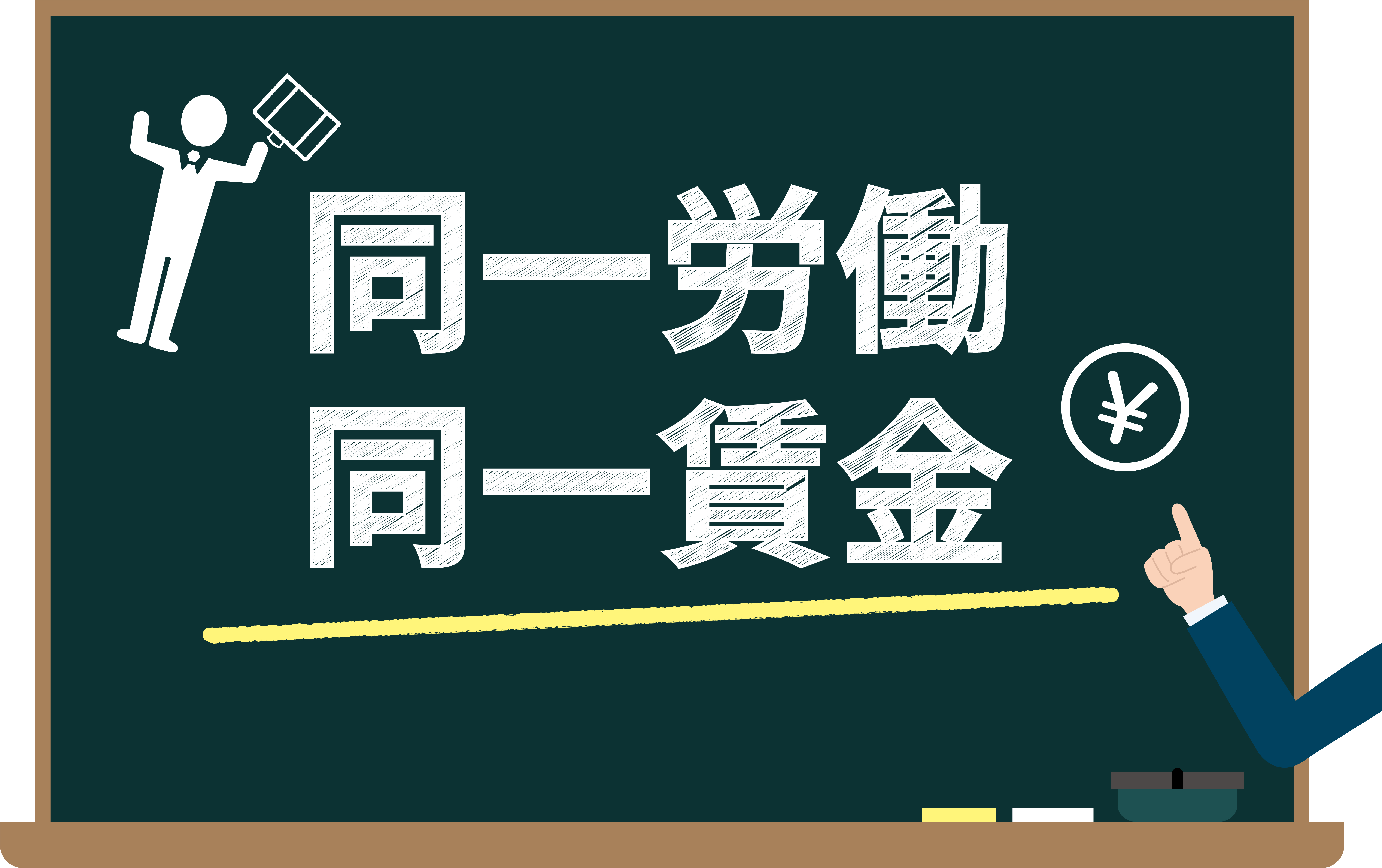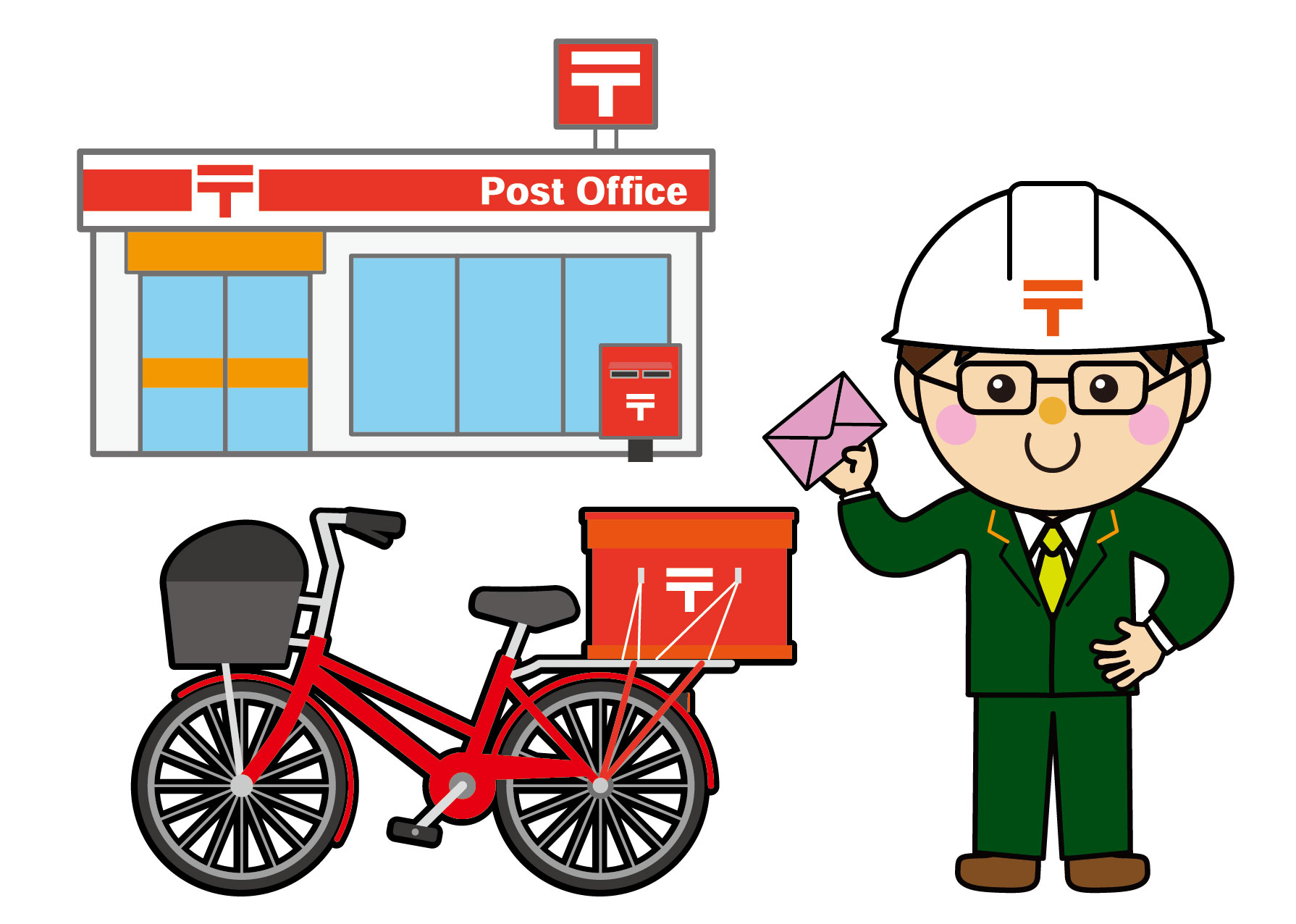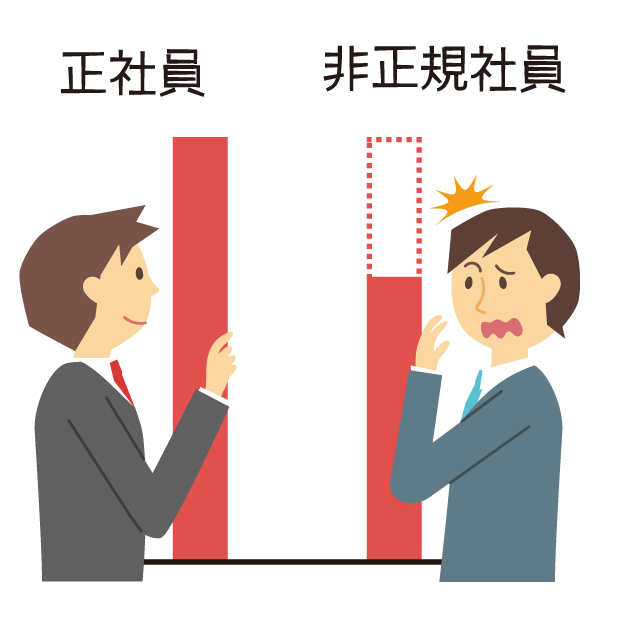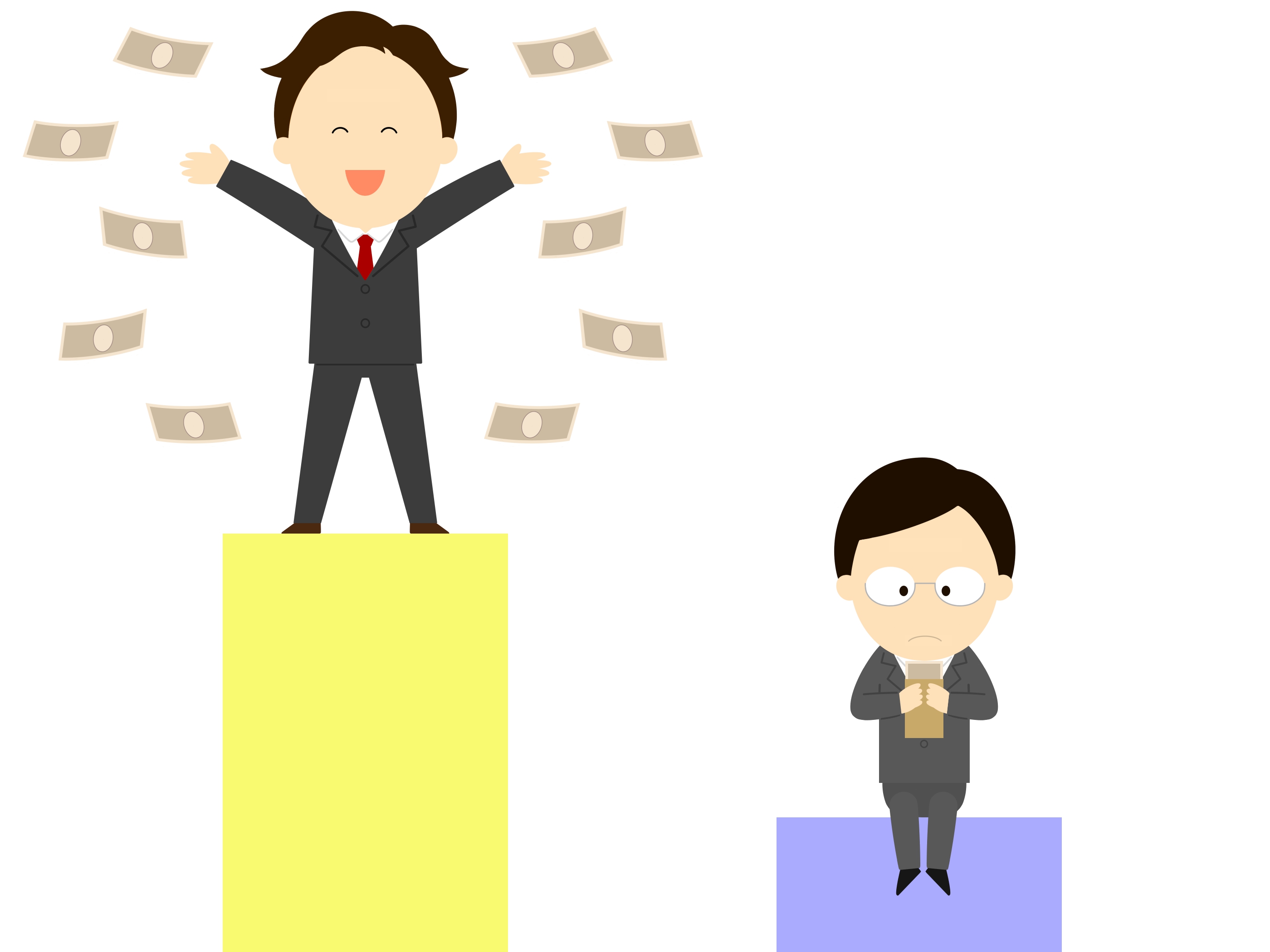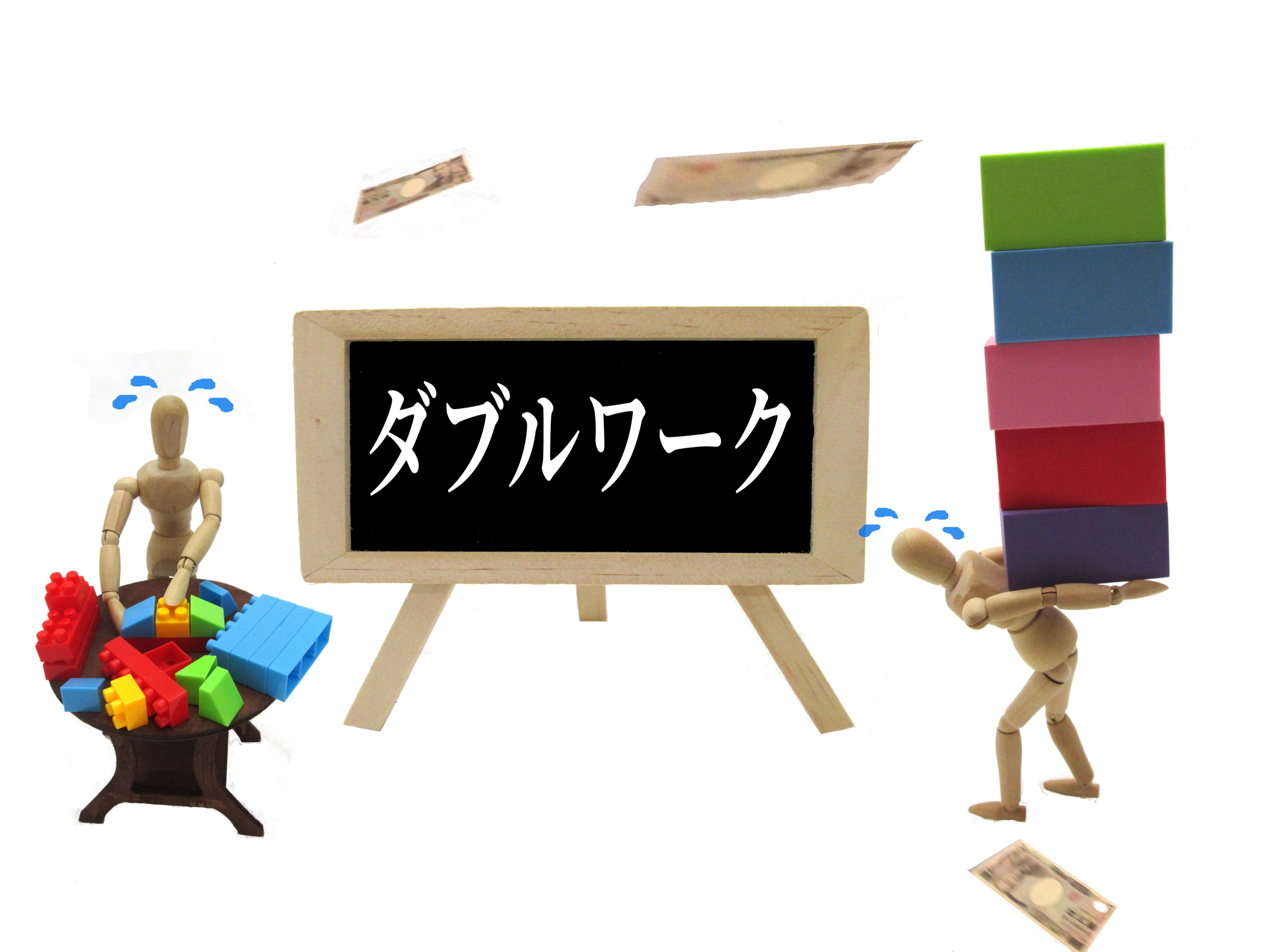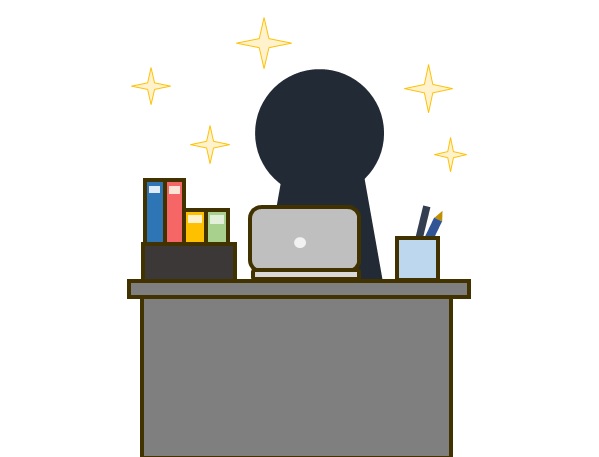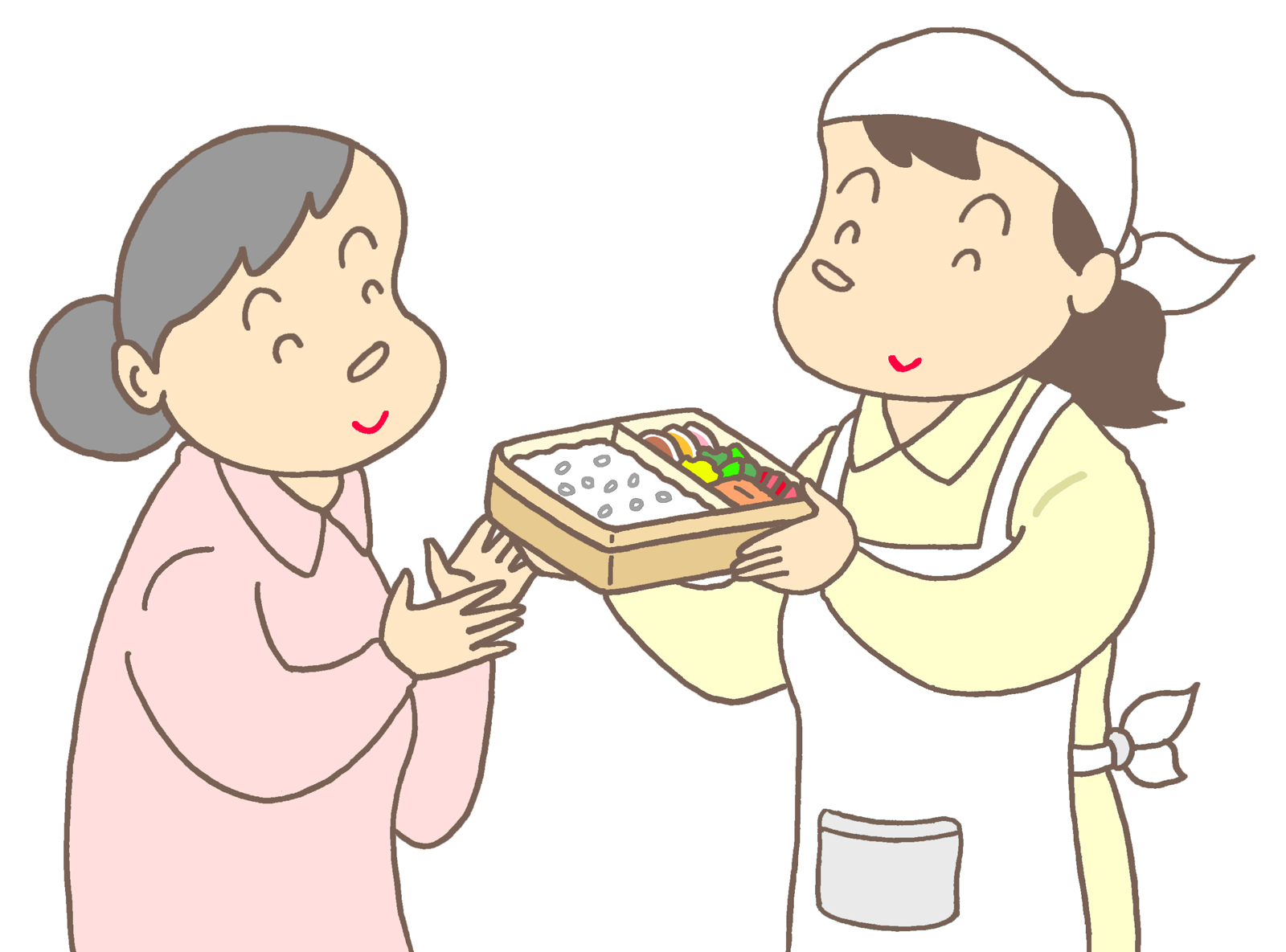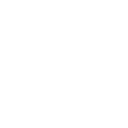職務手当が固定残業代の対価性の要件を満たさず無効とされた事件
1 未払残業代請求事件で固定残業代が争点になる理由
未払残業代請求事件では、会社がある手当を支払っていて、
その手当が残業代になるので、
未払の残業代はないと反論してくることがよくあります。
ある手当が定額の残業代として支払われていることを
固定残業代といいます。

残業代の計算は、時間単価×残業時間×割増率で計算されます。
時間単価は、基礎賃金÷月平均所定労働時間で計算されます。
この基礎賃金には、基本給や皆勤手当などが含まれるのですが、
固定残業代である手当も含まれるかが争点になります。
固定残業代である手当が残業代の支払として無効となれば、
固定残業代である手当が基礎賃金に含まれるので、
時間単価の金額が多くなり、結果として、残業代の金額も多くなります。
また、固定残業代である手当が残業代の支払として無効となれば、
会社は、一円も残業代を支払っていなかったことになりますので、
固定残業代として支払っていた手当とは別に
残業代を支払わなければならなくなります。
このように、固定残業代が有効になるか否かによって、
請求できる未払残業代の金額が大きく変わるので、
会社は、固定残業代について、激しく抵抗してくるのです。
2 固定残業代の対価性の要件
この固定残業代について、
労働者に有利に使える裁判例をみつけましたので紹介します。
サン・サービス事件の名古屋高裁令和2年2月27日判決です
(労働判例1224号42頁)。
この事件では、ホテルで働く調理師である原告が、
被告の会社に対して未払残業代を請求しました。
原告は被告から、深夜・残業手当とみなす職務手当13万円
の支給を受けていたところ、
この職務手当が固定残業代として有効かが争われました。
固定残業代が有効となるための要件として、
固定残業代とされている手当が、
時間外労働に対する対価として支払われるもの
とされていなければならないという、対価性の要件があります。
この対価性の要件を満たしているかについては、
日本ケミカル事件の平成30年7月19日最高裁判決において、
労働契約書の記載内容、
会社の労働者に対する当該手当や割増賃金の説明内容、
労働者の実際の労働時間などの勤務状況など
を考慮して判断することが明らかになりました。
本件事件では、以下の事実から、
職務手当は時間外労働の対価としては認められないと判断されました。
会社は、勤務時間管理を適切に行っていなかったこと。
職務手当は80時間の残業代に相当するのですが、
原告は、毎月120時間を超える時間外労働をしており、
実際の時間外労働と大きく乖離していること。

被告会社では36協定が締結されておらず、
時間外労働を命ずる根拠を欠いていること。
職務手当は、対価性の要件を満たさず、
固定残業代として無効となるので、
職務手当は基礎賃金に含まれることになりました。
被告会社は、36協定を締結していなかったので、
適法な時間外労働が観念できないことになるので、
職務手当を時間外労働の対価とするには無理があります。
職務手当が80時間の残業代に相当するとされていたのですが、
過労死ラインに設定されており、この点で無効になるとも考えられます。
3 通勤手当は基礎賃金に含まれるのか
また、この事件では、通勤手当が基礎賃金に含まれると判断されました。
通勤手当は、労働基準法37条5条において、
基礎賃金に含まれないと規定されているのですが、
ここで言う通勤手当とは、
労働者の通勤距離又は通勤に要する実際費用に応じて
算定される手当をいいます。
労働基準法37条5項の通勤手当は、
原則として実際距離に応じて算定されるものをいい、
一定額まで距離にかかわらず一律に支給する場合には、
実際の通勤距離や通勤に要する実際費用に
応じて定められたものとはいえず、
労働基準法37条5項の通勤手当に該当しないこととなり、
残業代を計算するにあたっての基礎賃金に含まれることになります。
通勤手当という名目にとらわれることなく、
実質的に検討する必要があるのです。
本日もお読みいただきありがとうございます。