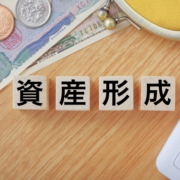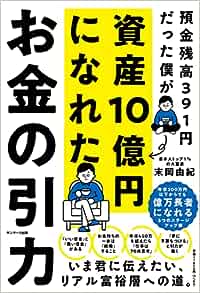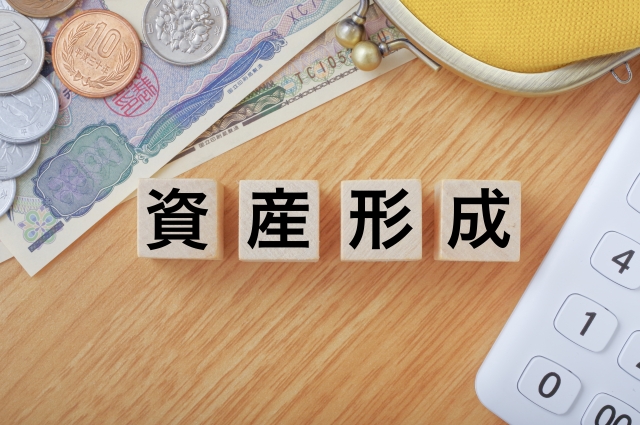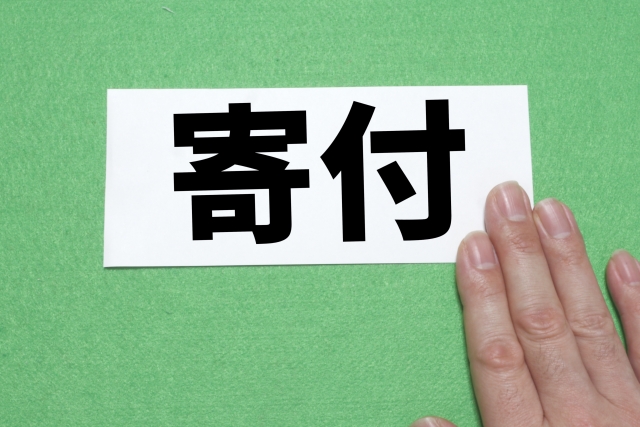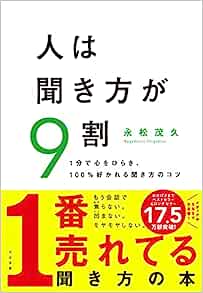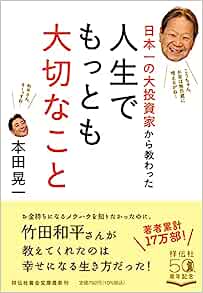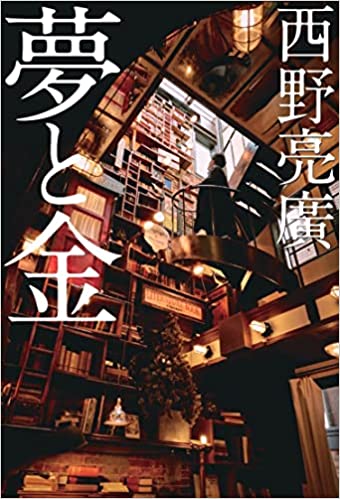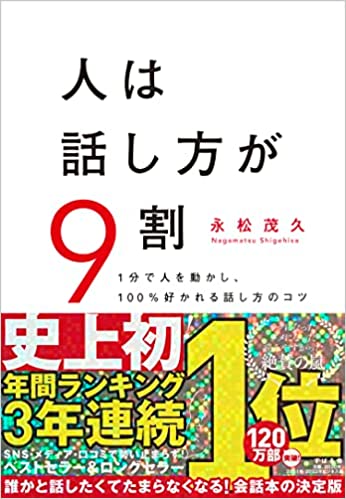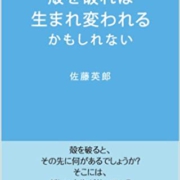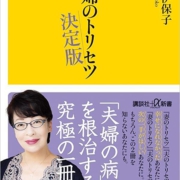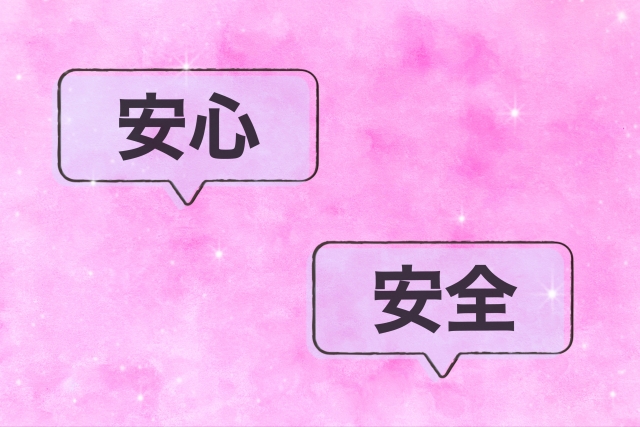すごい運の育て方
1 感謝神経を鍛える
Voicyパーソナリティの朝倉千恵子先生が、Voicyでご紹介されていた、
「すごい運の育て方」というムック本を読みました。
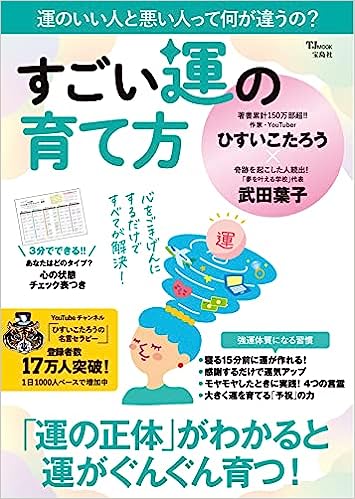
ひすいこたろう先生と武田葉子先生の共著で、運を良くするために、
日常、どのような習慣を身につければいいのかが、
とてもわかりやすく解説されています。
運がいいか悪いかは、とても抽象的な概念であり、
本当にそんなことを信じられるのかと疑問に抱く方がいらっしゃるかもしれません。
私は、運の良さは、生きていく上で、
とても大切な要素であると理解していましたが、
運とはなんなのかを深く考えたことはありませんでした。
この本を読み、運の正体とは、心の状態であると知りました。
そのため、運を良くするためには、心の状態を良くすればいいのです。
運と言うと、偶然の要素が多いように思えますが、
自分の心の状態であれば、ある程度、自分でコントロールすることができそうです。
すなわち、喜びや感謝といったごきげんな心の状態にすることで、
運を引き寄せることができるのです。
この本では、自分の心をごきげんな状態にするための、
日常生活における、ちょっとした習慣が紹介されていますので、
私が、実践したいと思ったことを3つ紹介します。
1つ目は、感謝神経を鍛えることです。
日常生活の中にある、小さな幸せを見つけて、感謝するのです。
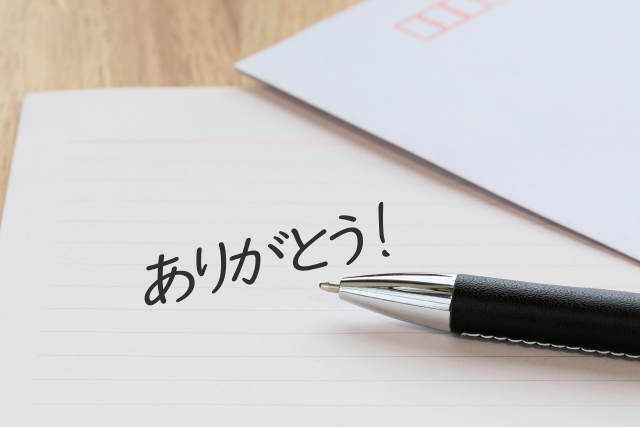
人は、つい、自分に無いものに目を向けてしまいがちですが、
実は、自分の周囲には、「ある」ものがいっぱいあるのです。
自分の周囲に「ある」ものに目を向ければ、
世の中には感謝することだらけであると気づきます。
例えば、私がこうしてブログを記載しているのは、
私の目の前にパソコンがあるからでして、
このパソコンが「ある」ことに感謝し、
このパソコンを作ってくれた人や会社にも感謝することができます。
このように、「ある」ことに気づくと、感謝の気持ちがわいてきます。
そして、感謝することを思いついたら、
「ありがとうございます。おかげさまで◯◯できています」と感謝してみるのです。
実際、「ある」ことに気づいて、感謝の気持ちを心の中でつぶやくと、
心が穏やかになり、感情が落ち着きます。
他にも、料理を食べる前に、
「この料理を作るためにどれだけの人がかかわっていたのだろう」と想像すると、
「ありがたい」という感謝の思いが芽生えます。
こうして、「ある」ことに気付いて、感謝していくと、
感謝神経が磨かれて、ごきげんに暮らせるようになるのです。
日常生活で、「ある」ことに気付いて、感謝していきます。
2 自分を褒める
2つ目は、自分を褒めることです。

自分のことを自分で褒められるようになると、
自分で自分の機嫌をとることができるようになります。
すると、相手のいいところも褒められるようになり、
他の人から愛されて、運がよくなるのです。
そう、まずは、自分を褒めることから実践するのです。
最近、私は、仕事が忙しい中、家族のために、洗濯等をしているとき、
「本当にお前はがんばっている」と自分を褒めて、自己肯定感を高めています。
家事をしている自分を褒めるのは、とても効果的です。
また、鏡の前で、最高の笑顔を作り、鏡の自分に対して、
「愛しているよ」、「大好きだよ」「がんばっているね」
と声をかけることもいいようです。
これは、予祝という、前祝いすることで、
その願いを引き寄せる、やり方なのです。
鏡の自分に話しかけるので、
自分に肯定的な自己暗示をすることにもつながります。
お風呂でやるのがよいようです。
毎日、鏡の前で、笑顔を作り、自分に肯定的な言葉を投げかけてみます。
3 自分をゆるす
3つ目は、自分を許すことです。

自分を許し、責めないことは、自分でいることが心地よく、
くつろげる状態になれます。
私は、ネガティブなことを考えたとき、自分を責める傾向にあります。
そのように、何か嫌な気持ちになったときには、
「~と思った自分を受け入れ、認め、許し、愛しています」
と心の中でつぶやくといいのです。
例えば、今日会う人に本当は会いたくないと思ったとしても、
「今日はあの人に会いたくないなぁと思った自分を受け入れ、認め、許し、愛しています」とつぶやくことで、
自分のネガティブな思いが緩和されます。
なにか、モヤモヤした思いになって、自分を責めるときには、
「~と思った自分を受け入れ、認め、許し、愛しています」とつぶやいてみます。
このように、運を良くするための、日常生活における、
実践しやすい習慣がたくさん紹介されていますので、
運をよくしたい方には、必見の本です。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。