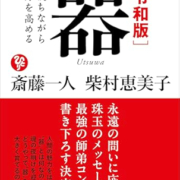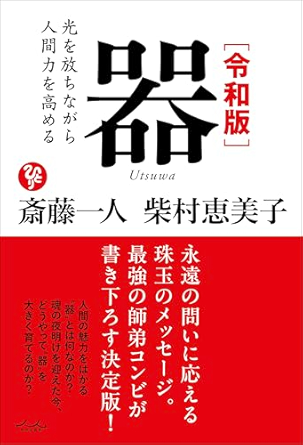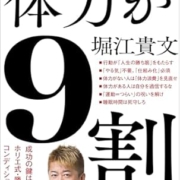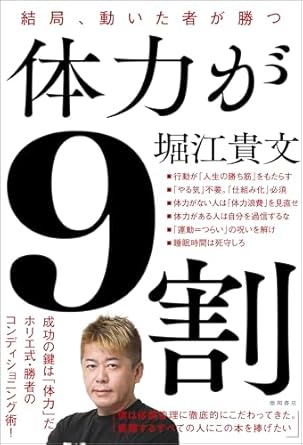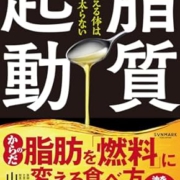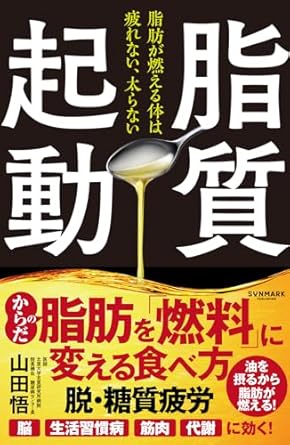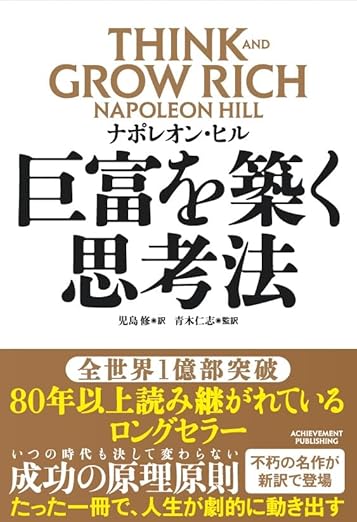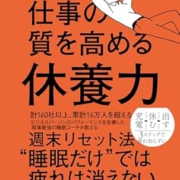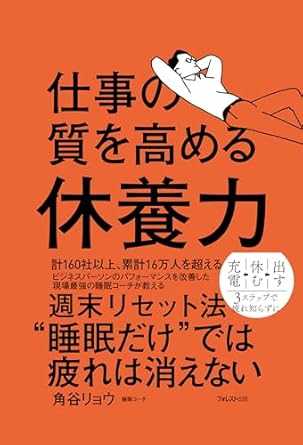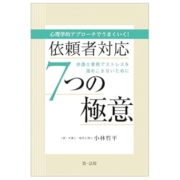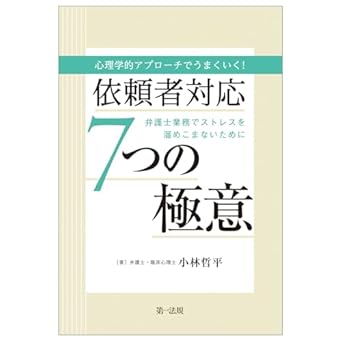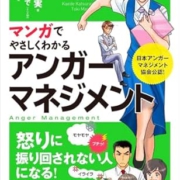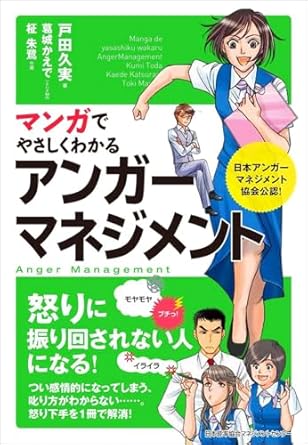気分の9割は血糖値
自分の体は、食べた物で出来ているので、最近は、食事に関する本を読んでいます。
そのような中、小池雅美先生の初の著書である「気分の9割は血糖値」という本を読みました。
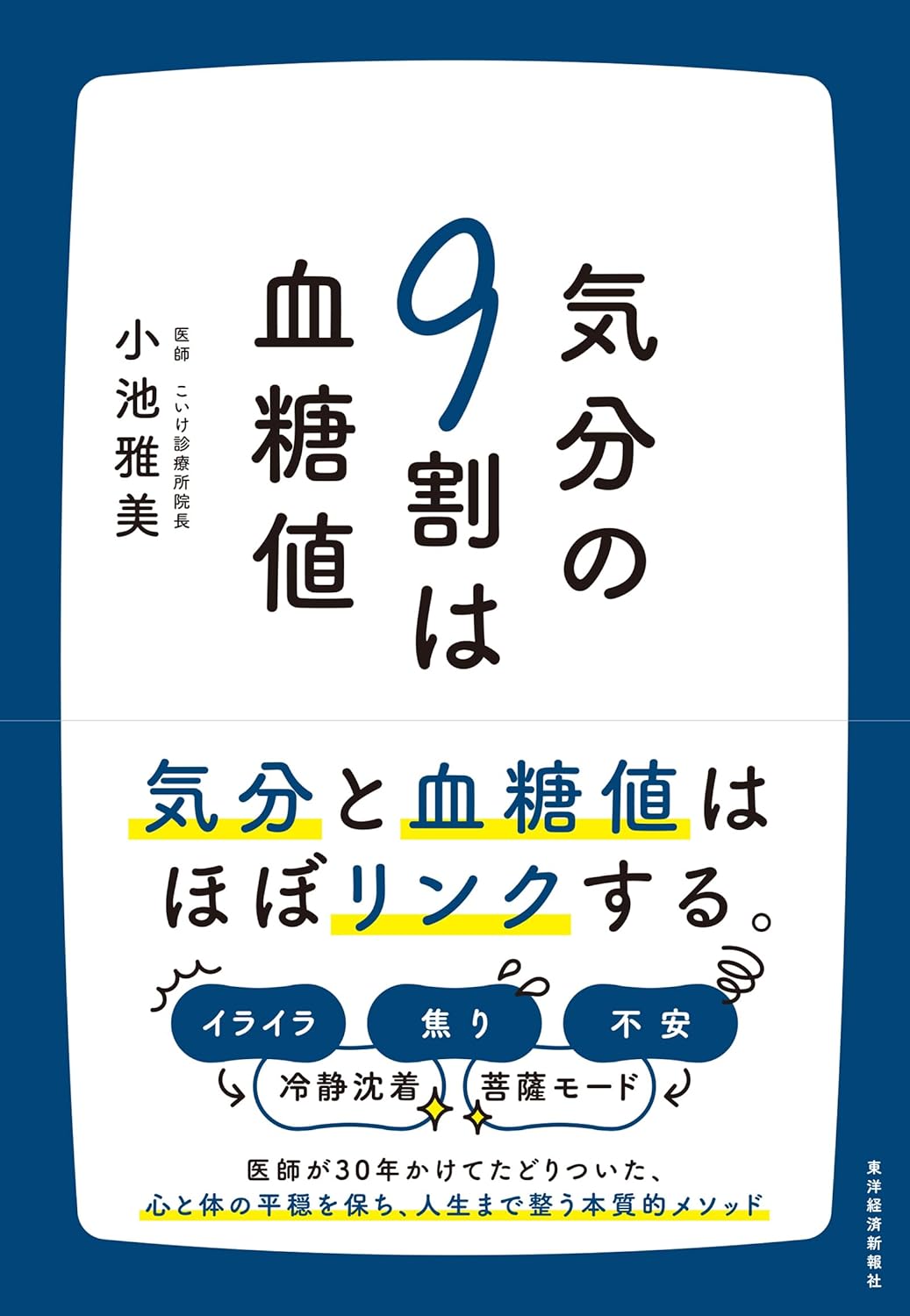
血糖値が乱高下する、血糖値スパイクの危険性について知っていたので、自分の血糖値がどのようになっているのかを調べるために、リブラという血糖値の測定機を使用していました。
すると、私の場合、血糖値スパイクはもちろんのこと、夜間に低血糖になっていることが分かりました。
夜間の低血糖について知りたくて、血糖値のタイトルに惹かれて、この本を読みました。
血糖値をコントロールすることが、仕事でパフォーマンスを発揮するために、重要であることが、分かりやすく解説された良書です。
今回は、この本を読んで、私が気付いたことを3つ紹介します。
1つ目は、夜間低血糖です。
私は、リブラという血糖値の測定機を使用していた時、夜間に、低血糖になっている日がありました。
夜間低血糖になっている時は、夜に目が覚めて、その後寝れなくなり、睡眠が不十分になっていました。
夜間低血糖になると、睡眠の質が落ち、翌日の仕事で集中力が切れるリスクがあります。
また、夜に成長ホルモンの分泌が足りなくなり、エネルギー切れになるリスクがあるのです。
血糖値のコントロールができていないと、夜の快眠と朝のパフォーマンス向上ができなくなるので、血糖値コントロールが重要であるかが分かります。
血糖値コントロールするためには、血糖値スパイクだけではなく、低血糖を回避して、血糖値を70~140の範囲に保つ必要があるのです。
2つ目は、鉄欠乏を防ぐことです。
ブドウ糖からエネルギーを作り出すためには、鉄が重要な役割を果たします。
すなわち、鉄が足りないと、エネルギー不足に陥り、パフォーマンスが上がりません。
また、鉄が不足すると、ヘモグロビンを十分に作ることができず、体や脳に酸素を運べなくなります。
そのため、鉄欠乏を防ぐために、食事で鉄を摂取する必要があります。
鉄を摂取するためには、動物性食品のほうが効率的で、レバー、ハツ、鰹等に鉄が多く含まれています。
また、煮干しや鰹節も、鉄の補給によいようです。
3つ目は、捕食をとることです。
血糖値は、食事をして3~4時間ぐらいは保たれますが、それ以降は、血糖値が下がり、エネルギー切れになってしまいます。
エネルギー切れになると、イライラしたり、集中力が途切れます。
また、エネルギー切れになると、筋肉を分解してエネルギーに変えようとします。
そうなると、筋肉量が減り、代謝が低下し、脂肪がつきやすい体になります。
逆に、血糖値が安定すると、筋肉の合成が促進されて、代謝が上がります。
特に、昼食から夕食までの時間は長いため、この時間帯にエネルギー切れが生じやすいです。
エネルギー切れを防ぐために、捕食をとります。
捕食は、エネルギー切れを防ぐためなので、糖質をとります。
あわせて、タンパク質も摂取します。
ゆで卵、干し芋、おにぎり、プロテインバー、小魚アーモンド、ドライフルーツ等が、捕食に向いています。
そして、捕食をとる分、普段の食事の量を制限して、カロリーオーバーにならないようにします。
3食と捕食で栄養バランスとカロリーを調整すると、血糖値コントロールができ、仕事でパフォーマンスを発揮できることにつながるのです。
このように、血糖値と仕事のパフォーマンスについて、とても分かりやすく記載されているで、ビジネスマンにおすすめの一冊です。
今回も最後までお読みいただき、ありごとうございます。