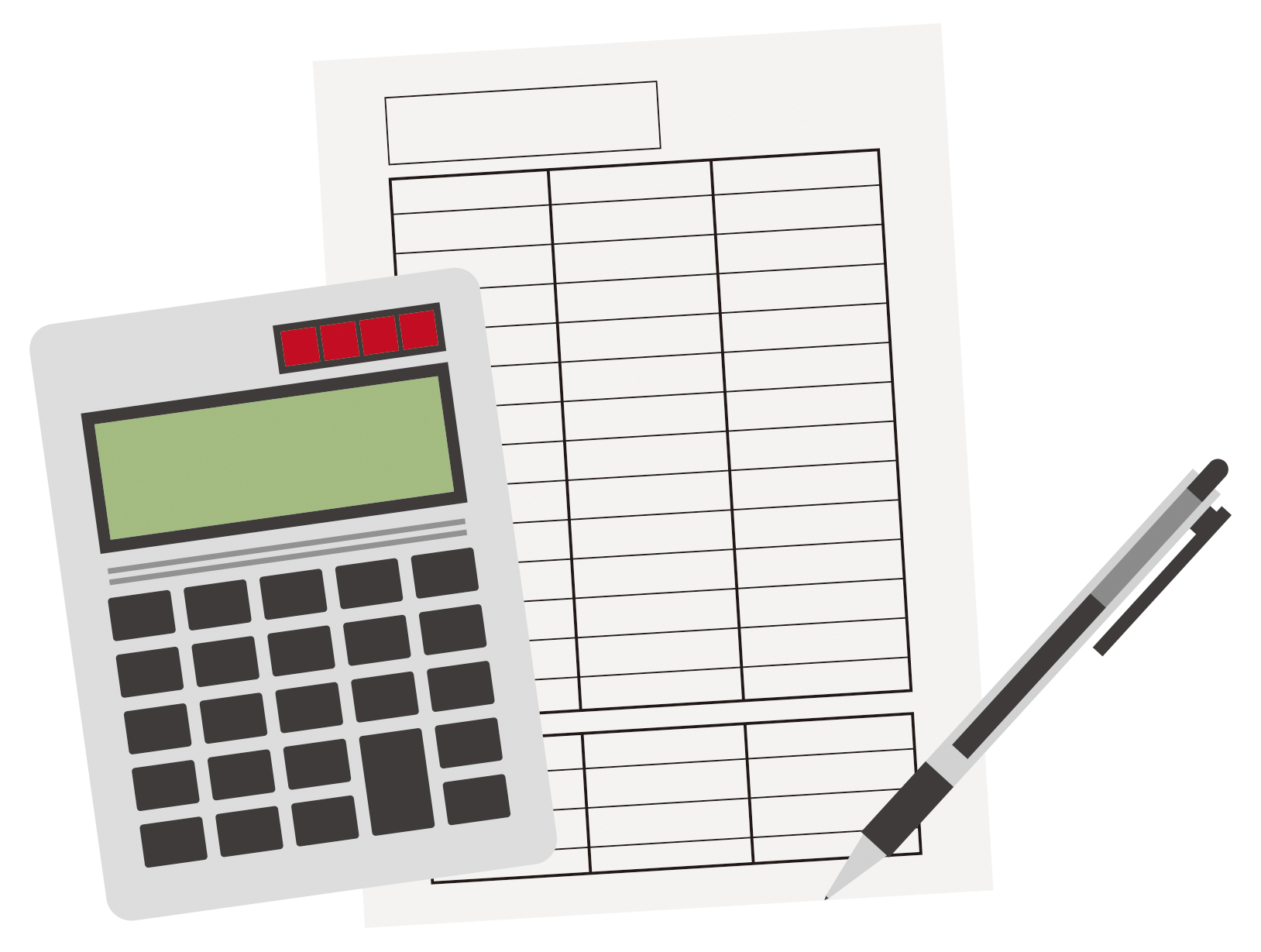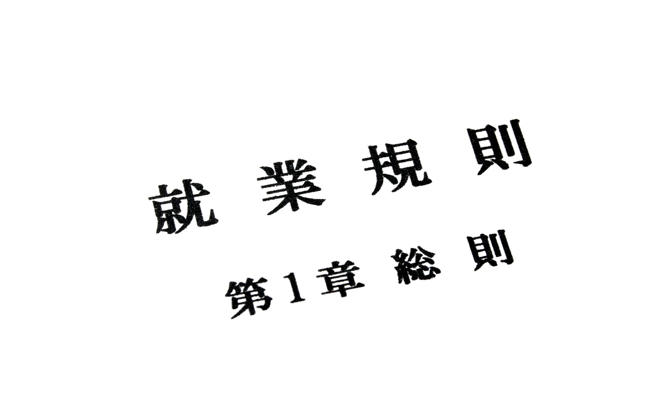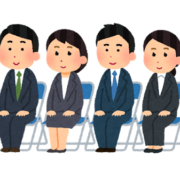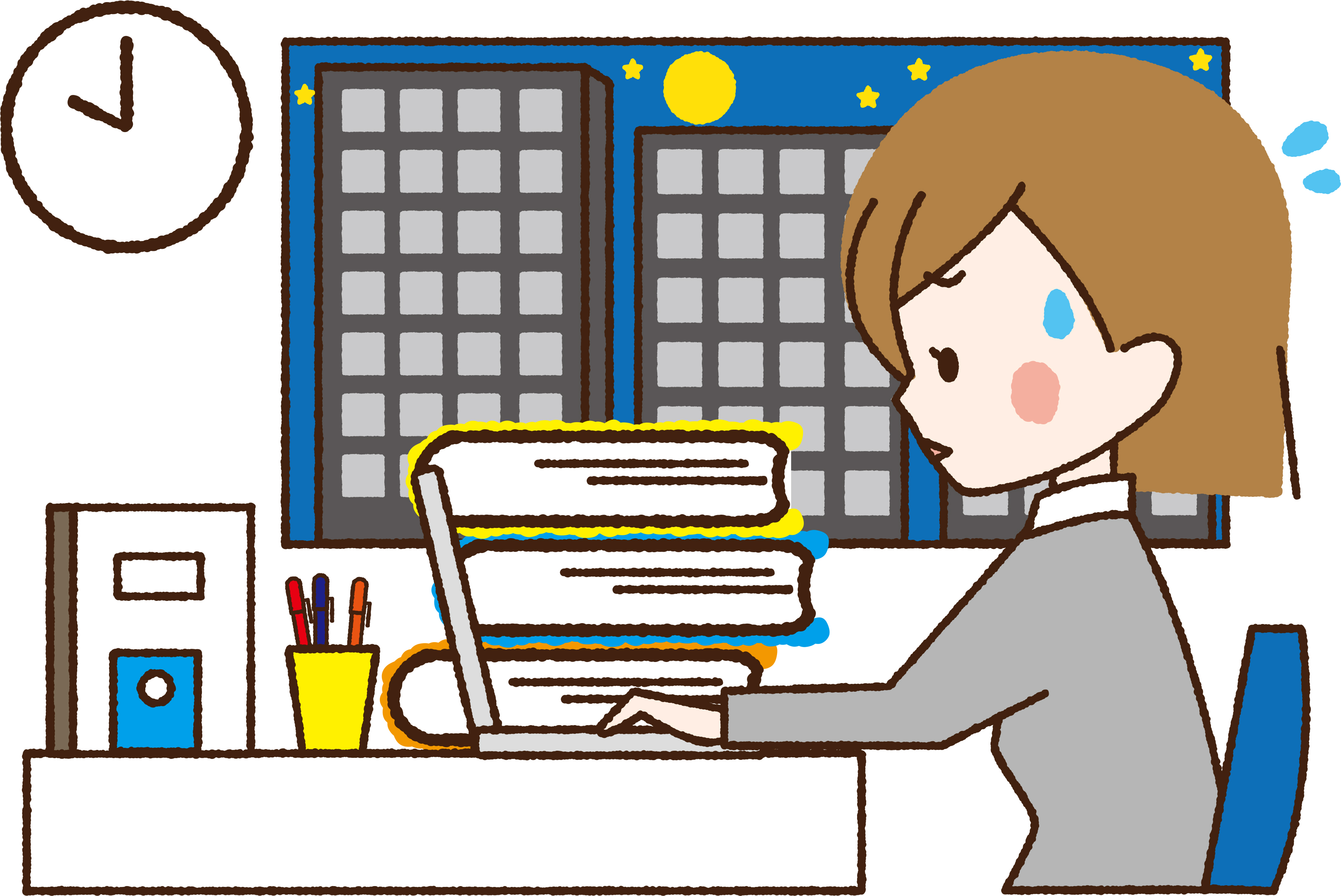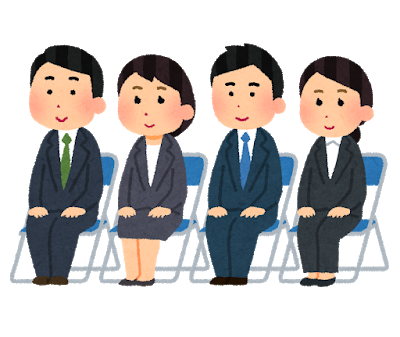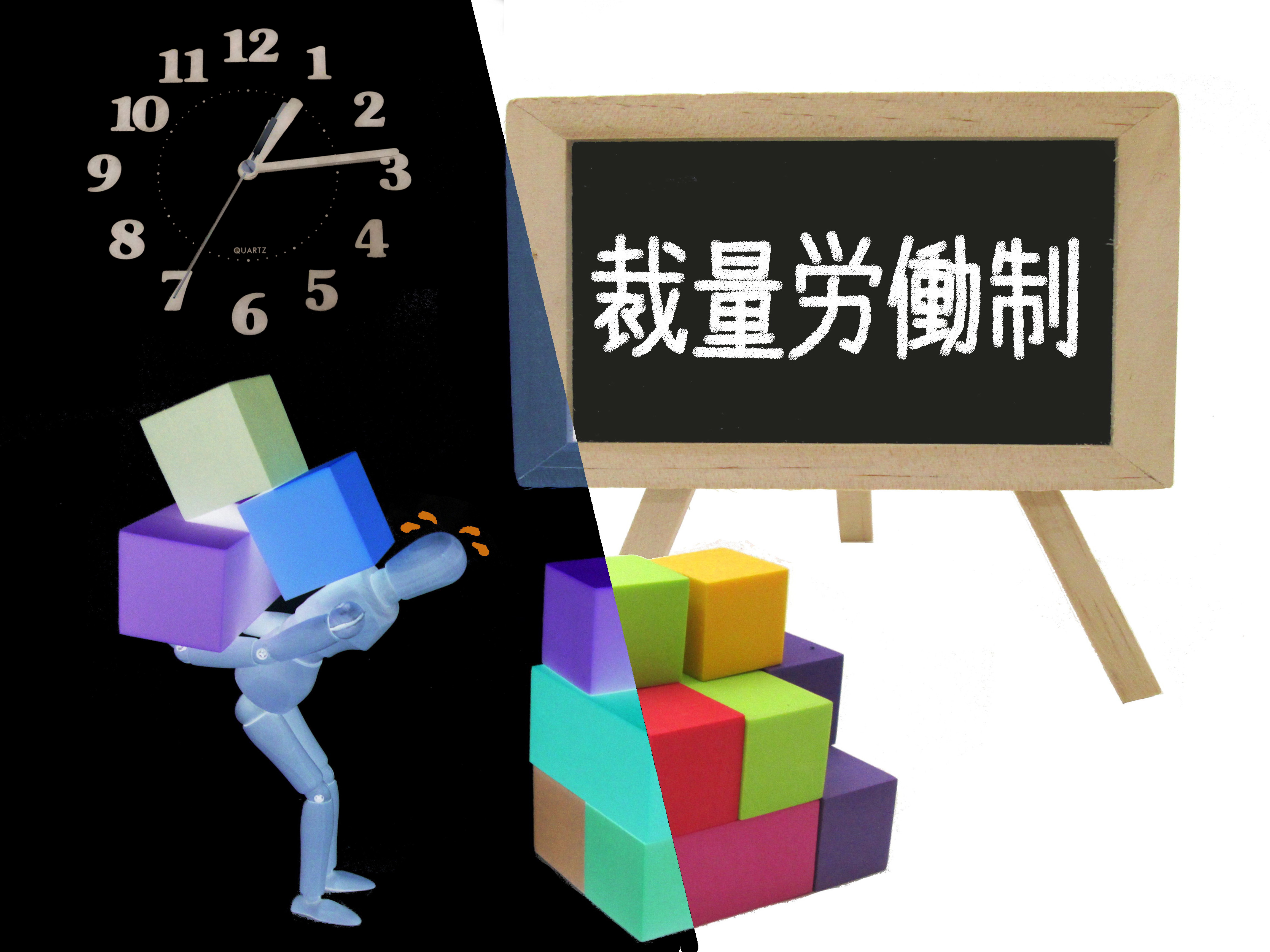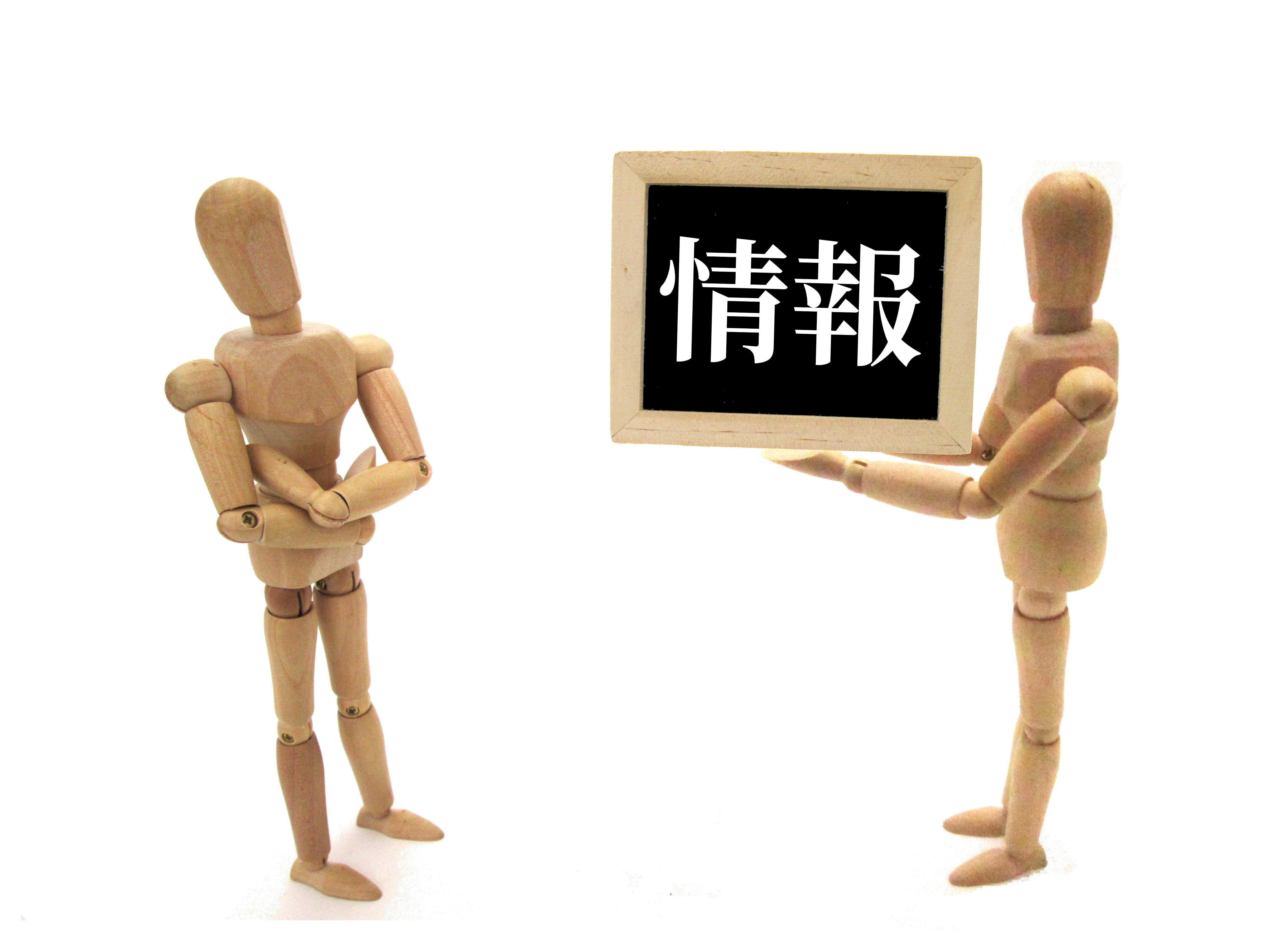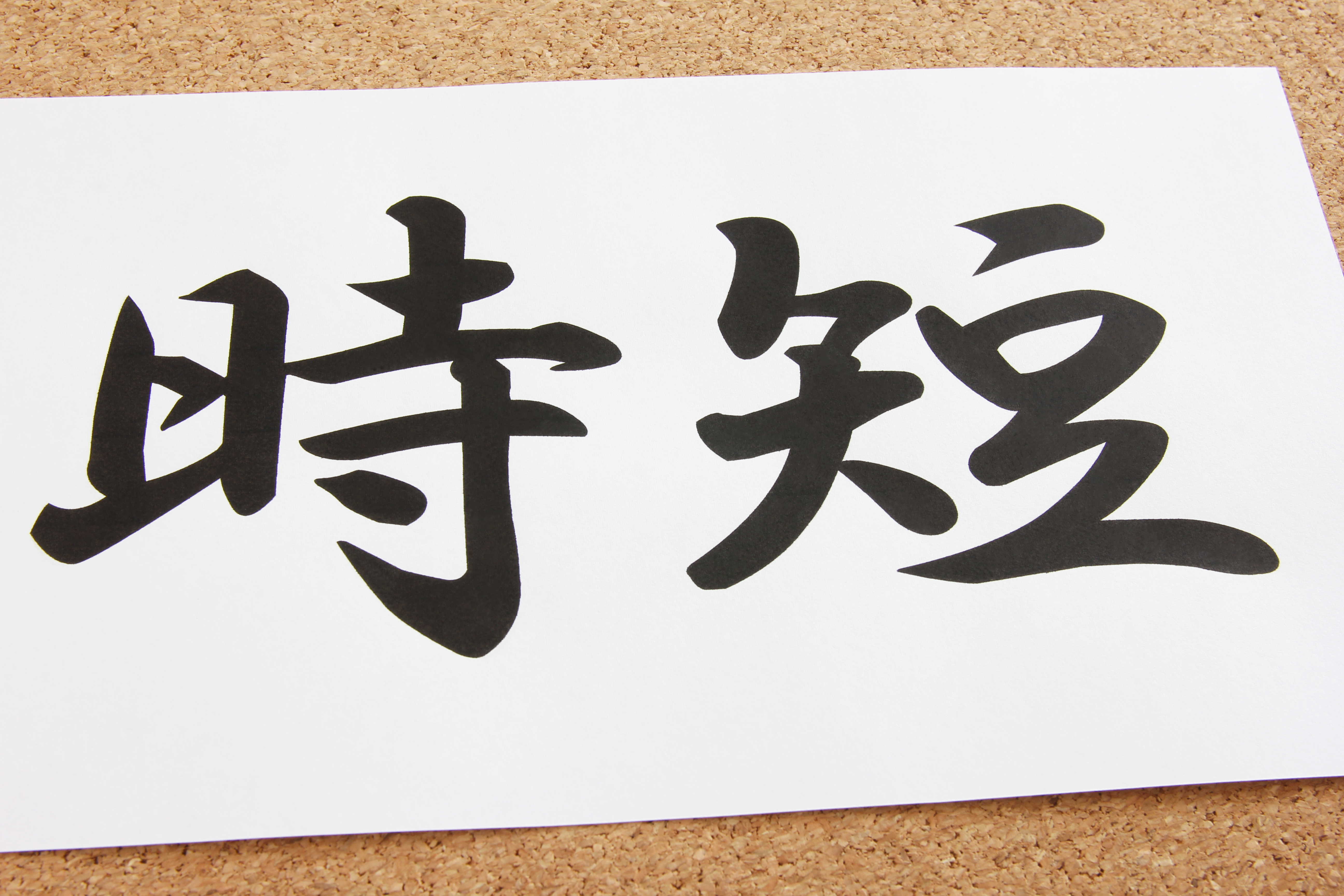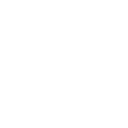未払残業代請求の消滅時効を中断するには
未払残業代請求の相談を受けた場合,
弁護士がまず検討すべきは,
消滅時効を中断することです。
2019年2月13日時点では,労働基準法115条により,
未払残業代請求権の消滅時効は2年となっております
(将来,労働基準法の改正によって
未払残業代請求権の消滅時効が5年になる可能性があります)。

未払残業代は,何もしないで放って置くと2年で消えてしまうのです。
例えば,給料が20日締めの当月末日払いの場合,
本日2019年2月13日時点であれば,
2017年2月分から2019年2月分までの
2年間分の未払残業代を請求できます。
しかし,2019年2月28日の給料支払日を経過して,
2019年3月1日以降になってしまえば,
2017年2月分の未払残業代請求権は消滅時効にかかり,
請求できなくなり,2017年3月分以降の
未払残業代しか請求できないのです。
そこで,消滅時効を止める必要があるのです。
消滅時効を止めることを,時効を中断するといいます
(民法改正により,時効の完成の猶予となります)。
未払残業代請求で,時効を中断するには,
労働者は,会社に対して,未払残業代を請求するように催告をして,
6ヶ月以内に労働審判の申立てや訴訟の提起をすればいいのです。
消滅時効を中断するための催告については,
未払残業代を請求する意思表示を明確に会社に知らせるために,
配達証明付内容証明郵便で通知するのが一般的です。

もっとも,内容証明郵便では,相手方が受け取らなかったり,
時間的な猶予がない場合には,特定記録郵便か,
送信リポート付きでファックス送信することもあります。
では,消滅時効を中断するための催告には,
どのようなことを書く必要があるのでしょうか。
昨日のブログで紹介したPMKメディカルラボ事件においては,
会社が,原告の通知には,請求金額やその内訳,
未払賃金の期間などが記載されていないとして,
消滅時効を中断するための催告にはあたらないと主張していました。
PMKメディカルラボ事件の東京地裁平成30年4月18日判決では,
催告とは,「債務者に対し履行を求める,債権者の意思の通知であり,
当該債権を特定して行うことが必要である」と定義し,
「債権の内容を詳細に述べて請求する必要はなく,
債務者においてどの債権を請求する趣旨か分かる程度に
特定されていれば足りる」と判断されました。
そして,原告の通知には,「賃金の未払いについて
(1)早出,休憩未取得,残業,休日出勤等に対して,
未払いである賃金を支払うこと。」という記載があり,
「資料提出について (2)過去2年間分の労働時間記録,
給料明細書のコピーを書面にて提出すること」と記載されていることから,
原告が会社に対して,原告の在籍期間のうち,
通知からさかのぼって2年間の時間外労働に対する
未払残業代の請求をしていると認められるとして,
催告にあたり,消滅時効の中断が認められました。
また,日本セキュリティシステム事件の
長野地裁佐久支部平成11年7月14日判決では
(労働判例770号98頁),
未払残業代を計算するのに必要な賃金台帳やタイムカードは
会社が所持しており,労働者が容易に計算できないことから,
消滅時効の中断の催告としては,
「具体的な金額及びその内訳について明示することまで
要求するのは酷に過ぎ,請求者を明示し,
債権の種類と支払期を特定して請求すれば,
時効中断のための催告としては十分である」と判断されました。
よって,消滅時効を中断するための催告としては,
「~年~月から~年~月までの残業代を含む全ての
未払い賃金を請求します。」と記載して,
会社に通知すればいいのです。

本日もお読みいただきありがとうございます。