ハラスメントの境界線3~様々なハラスメント対策~
昨日に引き続き,白河桃子先生の
「ハラスメントの境界線~セクハラ・パワハラに戸惑う男たち~」
についてのアウトプットを行います。
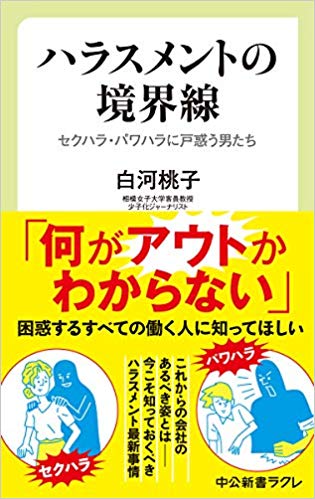
本日は,この本に記載されていたハラスメントの
防止策について紹介していきます。
企業がハラスメントを防止するための枠組みとして,
①ポリシーの表明,②窓口の設置,
③調査体制の整備,④是正措置・再発防止策
の4つが挙げられています。
白河桃子先生は,①ポリシーの表明として,
経営者が「ハラスメントを許さない」,
「ハラスメントにはこうした懲戒処分をする」
と明言することを提案されています。
厚生労働省が作成した「パワーハラスメント対策導入マニュアル」にも,
企業として,「職場のパワハラはなくすべきものである」という方針を,
トップのメッセージとして明確に打ち出すことが推奨されています。
ポリシーが表明されることで,職場において,
相手の人格を認め,尊重しあいながら仕事を進める意識が育まれ,
ハラスメントの被害者や周囲の労働者が,問題点の指摘や解消に関して
発言がしやすくなることが期待されます。
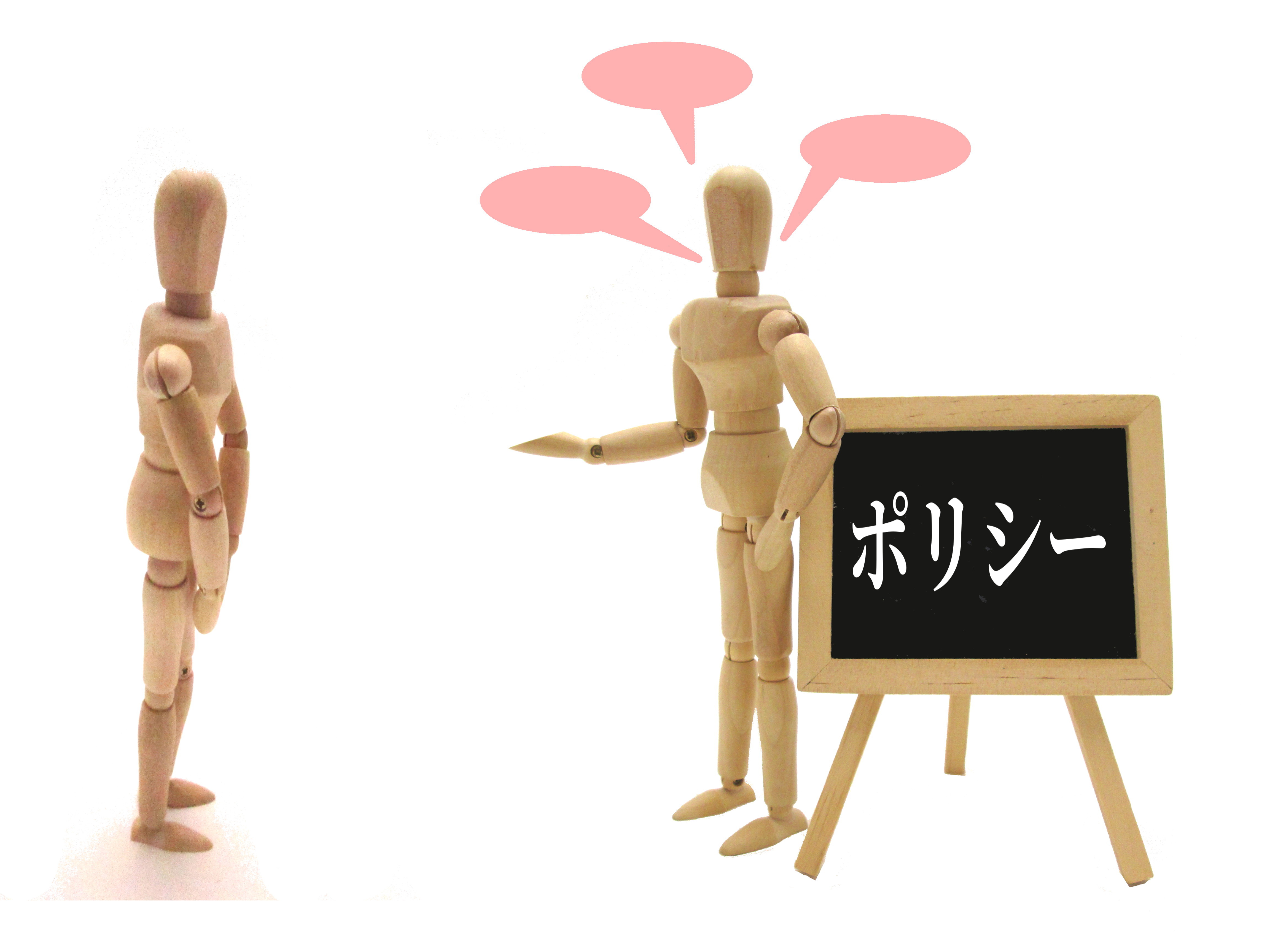
②窓口の設置については,昨日のブログに記載したとおり,
相談者が安心して相談できるように,
「独立性」,「非公開」,「匿名」が守られることが重要となります。
会社内における電話やメールなどの
「通報ホットライン」だけですと,
相談しにくいことも考えられますので,
第三者機関などに委託して外部窓口を設置するなど,
複数の窓口を整備すると,相談しやすい環境を
作れるようになるようです。
③調査体制の整備については,
中立的な立場で事実を確認し,
報復を禁止させる仕組みが必要になると思います。
④是正措置・再発防止策については,
管理職向けや一般従業員向けのハラスメント研修や,
パワハラは許されないことであることを
会社内で周知することが重要になってきそうです。
次に,最新のハラスメント対策を実施している企業が紹介されており,
その中の一つに,ビザ・ワールドワイド・ジャパンの
ハラスメントを目撃した人に通報義務があるというものがありました。

ビザ・ワールドワイド・ジャパンでは,
報復禁止方針を徹底した上で,
ハラスメントを目撃した社員は,
人事部に通報しなければならないようです。
安心して通報できる環境が整い,かつ,
企業が通報を義務化していることで,
ハラスメントを撲滅できるのかもしれません。
https://www.sbbit.jp/article/cont1/34691
また,通報窓口に相談することに躊躇する場合,
国内最大級のハラスメント改善プラットフォーム
「ソレハラ」というサイトがあります。
匿名で誰かの行為がハラスメントにあたるのかを,
ほかのユーザーに投票してもらう
「匿名ネコ裁判」というものがあります。
これってハラスメントかも?と思ったら,いきなり,
会社の窓口に相談するのはハードルが高いと感じたなら,
まずは,このサイトにゆるく問いかけてみるのもいいかもしれません。
そして,究極のセクハラ対策は,
管理職の多様性を進めていくことだと
白河桃子先生は提言しています。

日本の組織内で重要な意思決定をしている層は,
年齢や学歴,社歴などが同質な男性で構成されています。
同質性の高い組織では,「これくらいなら許される」という「本音」が,
「それは許されないことである」という建前とずれてしまい,
かつては通用した組織内の「本音」がすでに
社会で許されなくなってしまい,不祥事につながるというわけです。
財務省セクハラ事件を例にすれば,
「優秀な成績をあげていれば,多少セクハラは多目にみてもらえる」
という本音と,「セクハラをする人物は,
成績が優秀であっても組織にリスクをもたらす」
という建前がずれていたために問題が大きくなったと考えられます。
男性だけの同質な組織に,女性が進出すれば,
女性からの異なる意見がでることで,
本音と建前のずれに気付くことができます。
多様性のある職場では,
ハラスメントや不祥事が減る可能性がありそうです。
このように,様々なハラスメント対策が記載されていますので,
ハラスメントについて勉強するためには,
まず最初に読んでおいたほうがよい一冊だと思いました。
ハラスメントのある職場は,安心して働くことができない職場ですので,
多くの企業にハラスメント対策に取り組んでもらいたいと思います。
本日もお読みいただきありがとうございます。



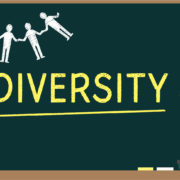
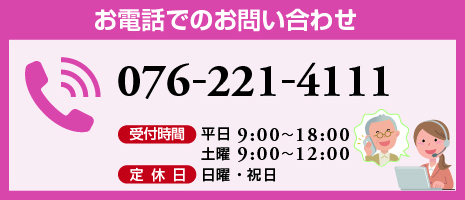
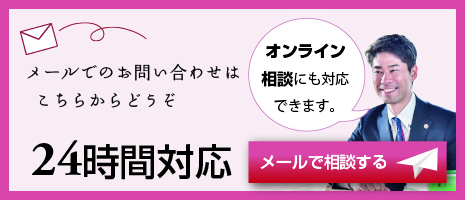




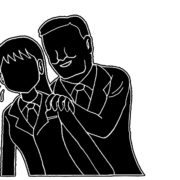









返信を残す
Want to join the discussion?Feel free to contribute!