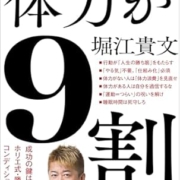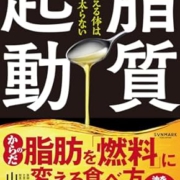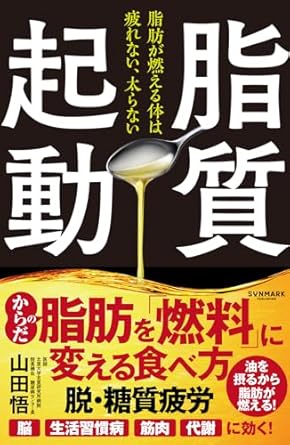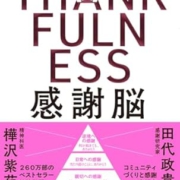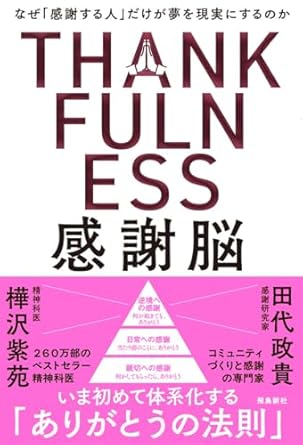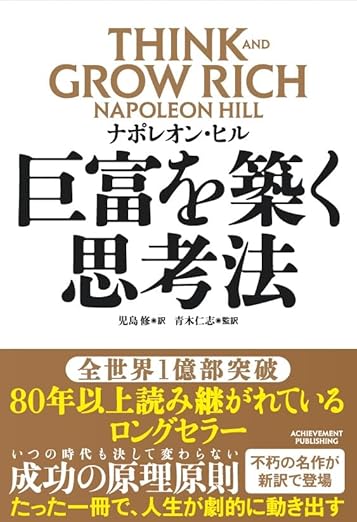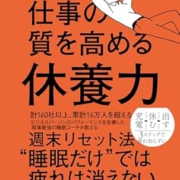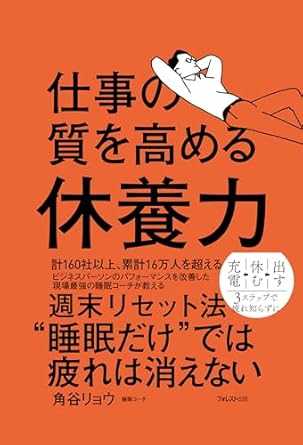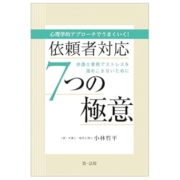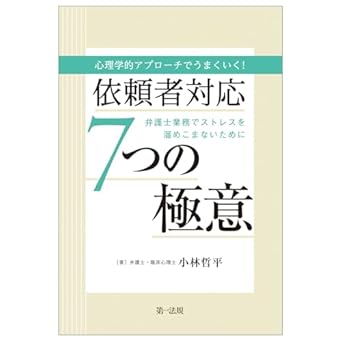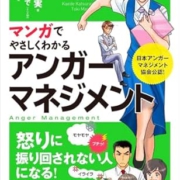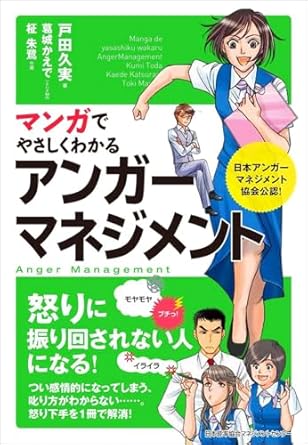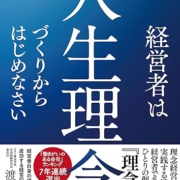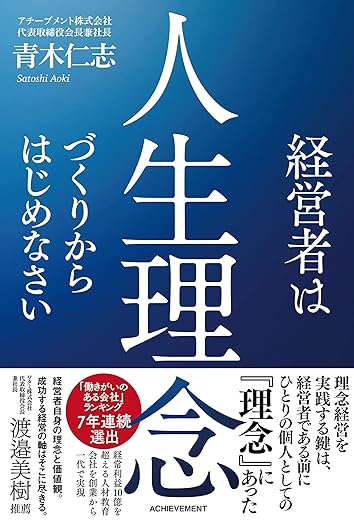体力が9割
堀江貴文氏の著書「体力が9割」を読みました。
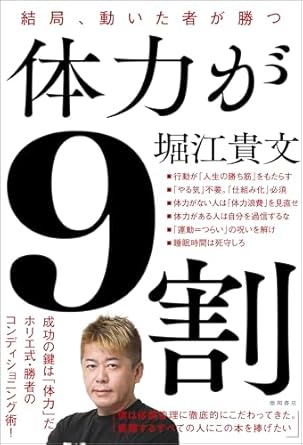
40代になり、なんとなく体力の衰えを感じるようになり、体力の大切さを実感していたため、この本を読みました。
体力オバケであるホリエモンが実践しているコンディショニングの詳細が、分かりやすく、熱く記載されているため、体力を向上させたい人にとって、おすすめの一冊です。
今回は、私がこの本を読んで得た気付きを3つ紹介します。
1 量質転化
1つ目は、量質転化です。
よく、仕事において、質が大事なのか、量が大事なのかという議論があります。
ホリエモンの答えは、ひたすら量をこなすです。
量をこなすことによって、仕事の知識、技術、経験が蓄積され、やがて仕事の質が向上するのです。
量を制する者が、質を制するのです。
あくまで、仕事の目的は、質の高い成果を生み出すことにあるのですが、それは、多くの量をこなさないと実現できないのです。
目的は質ではあるが、量はその手段になるわけです。
ホリエモンは、人の2倍はやろうと提唱しています。
人の2倍頑張るためには、体力が必要となります。
この体力を維持、向上させるための日々の実践が重要になります。
2 食に貪欲になる
2つ目は、食に貪欲になることです。
栄養バランスのとれた食事をとるのは理想ですが、出張や飲み会が重なると、栄養バランスに配慮することは難しくなります。
ホリエモンは、「ことさら栄養バランスを意識する必要なんてない。理想的な食事は本当に美味しいものを好きなだけ食べることだ」と伝えています。
私は、出張になると、野菜を食べる量が少なくなるので、自宅に帰ってきたときには、無性に野菜を多く食べたくなります。
体が欲しがっているものを食べると、自然と栄養バランスが整えられるということです。
そのため、ホリエモンは、美味しいものを求めて、舌と体を喜ばせてあげれば、結果的に、多様な栄養摂取につながると説明しているのです。
自分の体に、何を食べたいか、何を欲しているかを質問し、その日に食べるものを決めていきます。
そして、食は、体だけではなく、心もつくります。
すなわち、心の状態は、脳内で分泌される神経伝達物質に影響されるところ、神経伝達物質の原料は、肉、魚、大豆などに含まれるアミノ酸、ビタミン、ミネラルです。
心の状態を整えるために、食事から栄養素を取り入れる必要があります。
私は、美味しい食事をすることが楽しみの一つなので、これまで以上に、食を楽しんでいきます。
3 マッサージは投資
3つ目は、マッサージは投資であることです。
ホリエモンは、マッサージは、次のタスクに向けて、もう一度エネルギーを蓄える、未来への自己投資と伝えています。
長時間のデスクワークをしていると、血流が滞り、老廃物溜まることで、体が緊張し、自律神経が乱れて、血管が収縮します。
この体の乱れを整えるのがマッサージです。
マッサージによって、体という資本を常にメンテナンスするのです。
そして、マッサージは、信頼できるプロに施術してもらうのがよく、格安店ではなく、信頼できるプロに依頼すべきです
ホリエモンは、タイ古式マッサージをおすすめしていました。
私は、まだ、タイ古式マッサージを受けたことがないので、一度、施術を受けてみます。
仕事でバリバリ活躍したい人に役立つ内容がたくさん記載されている、おすすめの一冊です。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。