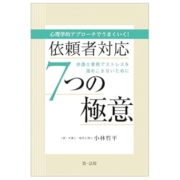心理的アプローチでうまくいく依頼者対応7つの極意
弁護士でかつ臨床心理士である小林哲平先生の著書「心理的アプローチでうまくいく依頼者対応7つの極意」を拝読しました。
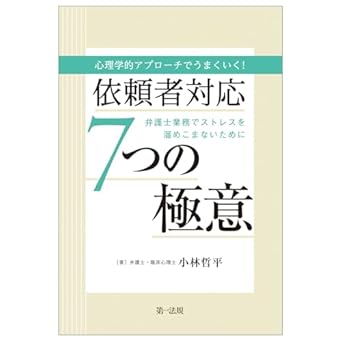
経験豊富な弁護士が、過去の依頼者対応の経験に基づき、効果的な依頼者対応について記載された書籍はありますが、弁護士の依頼者対応について、心理的アプローチから記載された書籍はあまりなく、新しい発見を得ることができます。
心理学の立場から、弁護士が依頼者に対してどのように対応するのが効果的かについて、わかりやすく記載されており、また、ストレスの多い弁護士が、メンタル不調に陥らないようにするための具体的なノウハウも記載されており、学びが大きいです。
今回は、この本を拝読して、私が得た気付きを3つ紹介します。
1 枠組みの設定
1つ目は、枠組みを設定することです。
枠組みとは、時間、場所、料金等種々の事柄に関する援助者と被援助者との約束事、ルール、制限のことをいいます。
例えば、相談時間は、60分という時間の枠を設定しておけば、相談者は、その時間内で話をしようとし、弁護士もその時間内で終えられるよう時間をコントロールするようになります。
このように時間の枠を設定すれば、不要なことに話がそれることを回避でき、相談者は、60分という時間を、自分の相談のために有効に活用しようと考えます。
また、60分の法律相談の料金は11,000円(税込)という、料金の枠を設定すれば、相談者は、料金の支払いがあるからこそ、友達の悩み相談とは一線を画する、専門家と被援助者という関係性が明確になります。
このように、弁護士と相談者との間で、取り決めがあり、それが守られていることで、専門家と被援助者という関係性が明確になります。
弁護士は、時間、場所、料金が決まっているからこそ、その時間のあいだ、本当に全エネルギーを使うことができるという側面があります。
依頼者に対して、枠組みを、丁寧に説明していこうと思います。
2 人の話を聞く時の姿勢
2つ目は、人の話を聞く時の姿勢です。
傾聴のスキルとして、アイコンタクト、うなずき、あいづち、要約、質問などがあり、コーチングを勉強していると、これらの具体的なやり方を学ぶことができます。
私は、傾聴のスキルを意識して使っていましたが、傾聴の際の自分の姿勢にまでは、意識が回っていませんでした。
傾聴する際は、椅子の背もたれに背中をつけるよりは、やや前傾姿勢をとると、相手の話に関心があることを態度で示すことができます。
また、傾聴する際、手の位置は、テーブルの下ではなく、テーブルの上に置くのがよいようです。
手をテーブルの下に置くと、不安や緊張、警戒心を示し、会話に消極的な態度とされてしまいます。
他方、手をテーブルの上に置くと、相手に対して、安心感や信頼感をもっていることや、会話に対する意欲を示すことができます。
相手に対して、安心感を与えるためにも、法律相談の際には、手をテーブルの上に置くなど、相談者の見える位置に置くようにします。
3 納得感
3つ目は、依頼者の納得感です。
裁判は、勝つこともあれば、負けることもあります。
不思議なことに、裁判に勝っても納得できない依頼者もいれば、負けても納得する依頼者もいます。
弁護士は、事件を解決するに際して、依頼者に納得感を持ってもらうことが大切になります。
では、依頼者に納得感を持ってもらうにはどうすればいいのでしょうか。
この書籍には、納得には、①自分にとって確かな利益が確認できる状況、②自分から能動的、主体的に関わること、③信頼できる他者の関与が必要とされています。
弁護士業務に当てはめると、①依頼者自身がその判断が最善だと考えること、②依頼者に主体的に事件に関与してもらうこと、③弁護士が依頼者と信頼関係を築き、法律の専門家としての説明を尽くし、依頼者の判断をサポートしていることが、依頼者の納得感につながるのです。
弁護士は、事実と証拠に基づいて、解決に向けて、メリットやデメリットをわかりやすく説明して、最終的な意思決定を依頼者にしてもらうことが大切です。
弁護士の意見を依頼者に押し付けることは、依頼者の納得感が得られず、避けるべきです。
これからも、依頼者に納得して、事件を解決してもらうために、依頼者に対して、丁寧に説明して、最終的な意思決定をしてもらいます。
弁護士が依頼者対応で、ストレスを溜め込まないためのノウハウがふんだんに盛り込まれている書籍なので、弁護士にとって必読の書だと思います。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました