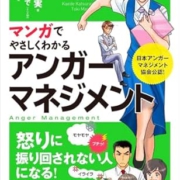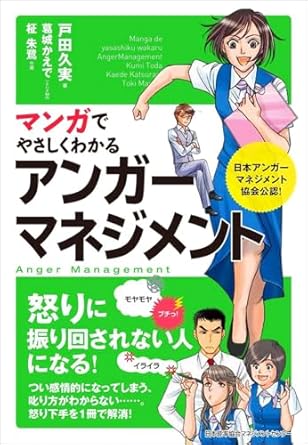君に成功を贈る
中村天風先生の「君に成功を贈る」という書籍を読みました。

この本は、過去に、司法修習時代の同期が勧めてくれたもので、一度読んで、心を積極的にすることを学びました。
そして、最近、岩本初恵先生のボイシーの中で、天風哲学を聞くようになり、過去に読んだ、この本をもう一度読み返し、中村天風先生のありがたいお言葉を学び直しました。
それでは、今回は、この本を読んで私が気付いたことを3つ紹介します。
1 他人に好かれる人間になる
1つ目は、他人に好かれる人間になる大切さです。
中村先生は、出世成功する人は、誰からも好かれる人であり、自分で他人に好かれる人間になろうと努力することが重要であるとおっしゃっています。
他人に好かれる人間になるためには、真心の親切でもって他人に接することです。
真心の親切とは、自分のことをするときと同じ気持ちで他人のことをしてあげればいいのです。
また、絶対に他人に迷惑をかけないことです。
どんな場合でも自分の言葉や行いで、他人に迷惑をかけないようにしなければなりません。
そして、他人から受けた恩義はもちろん、どんなささいな事でも、他人の好意は常に大きな感謝で受け入れることです。
当たり前のことと言えば、当たり前ですが、できているかと言われれば、できていないこともあります。
他人からモテている人は、習慣的に、これらのことを実践されています。
己の欲することを他人にも施すという黄金律を実践していきます。
2 積極的な心の態度
2つ目は、心の態度を積極的にすることです。
中村先生は、人間の神経系統の動きを堅持するには、積極的な心の態度が必要であるとおっしゃっています。
いつも積極的な心の状態を保たないと、神経系統は、うまく働かず、肉体が故障してしまいます。
積極的な心とは、「尊く、強く、正しく、清く」ということです。
心が積極的になれば、自然良能作用が働き、6つの生きる力が働き出します。
6つの力は、体力、胆力、判断力、断行力、精力、能力です。
この6つの力を作るためには、いかなる場合でも、心の力を落としてはならず、終始一貫、積極的な心の態度で人生を生きるのです。
心を積極的にするために、マイナスの言葉を回避して、自分自身にかける言葉や、他人に伝える言葉をプラスのものにしていきます。
日々の生活の中で、自分の心が積極的になっているか、定点観測していきます。
3 マイナスを受ける方法
3つ目は、マイナスを受ける方法です。
怒り、恐れ、悲しみ等のマイナスの感情を抱くようなことがあった場合、どのようにして受け止めるのか効果的かといいますと、まずぐっと腹に力を入れます。
そして、同時に肛門の穴を閉めて、肩を落とします。
腹、肛門、肩を同時に動かします。
腹でマイナスを受け止める際に、へそを中心とした腹筋神経から、脊髄の神経系統をもってして、心の乱れを防ぐことができるのです。
また、肛門を閉めると、人間の生命の強さが違うようです。
自分にとってマイナスなことがあった場合には、腹に力を入れて、肛門を閉めて、肩を落として、マイナスの影響を極力少なくしていきます。
この本に書いてあることを、真に理解するには、まだまだ修行が足りていないため、岩本初恵先生のボイシーで学びながら、折に触れて、読み返していく必要があると感じました。
人生を成功させたい人におすすめの一冊です。