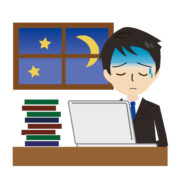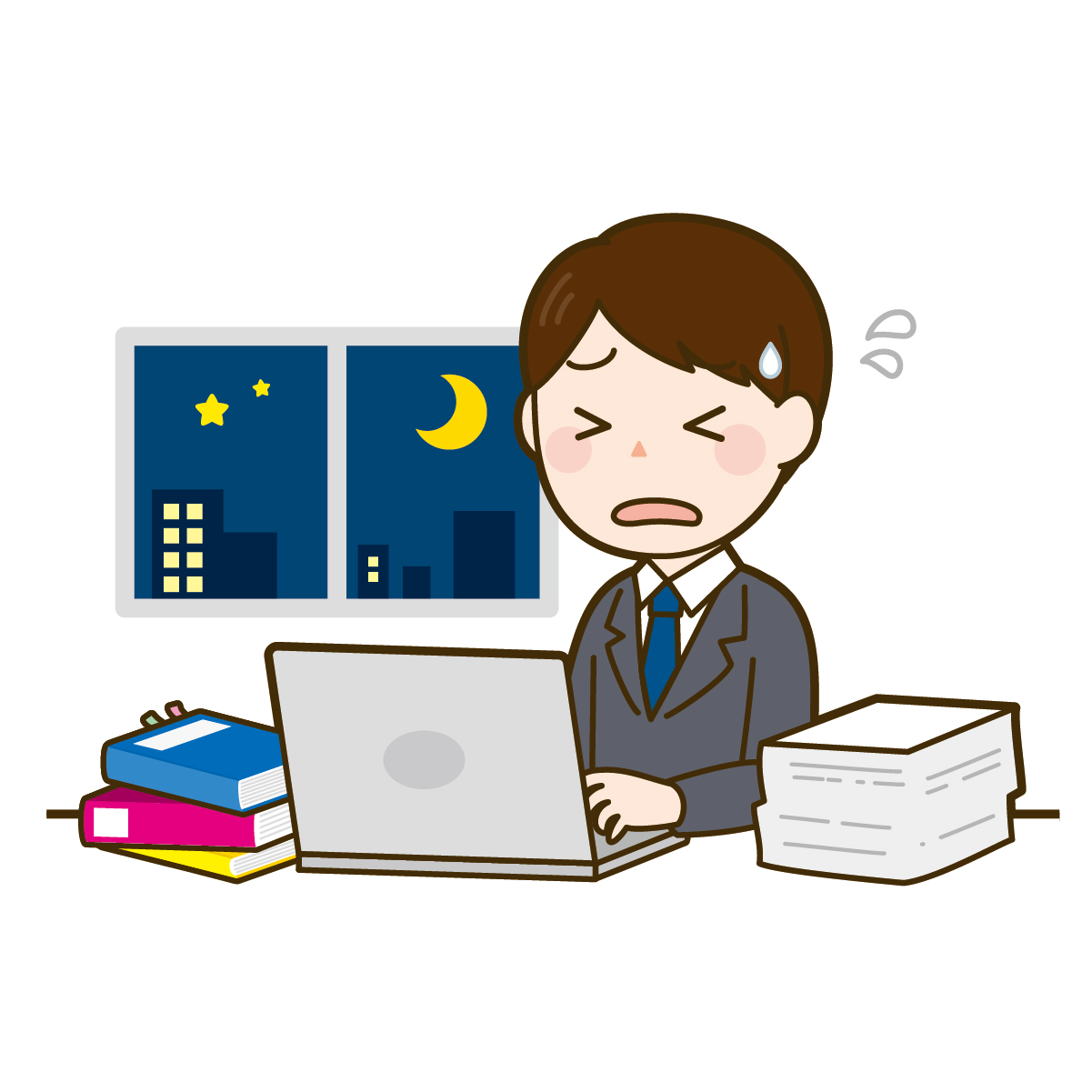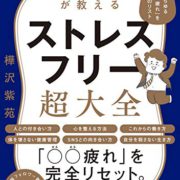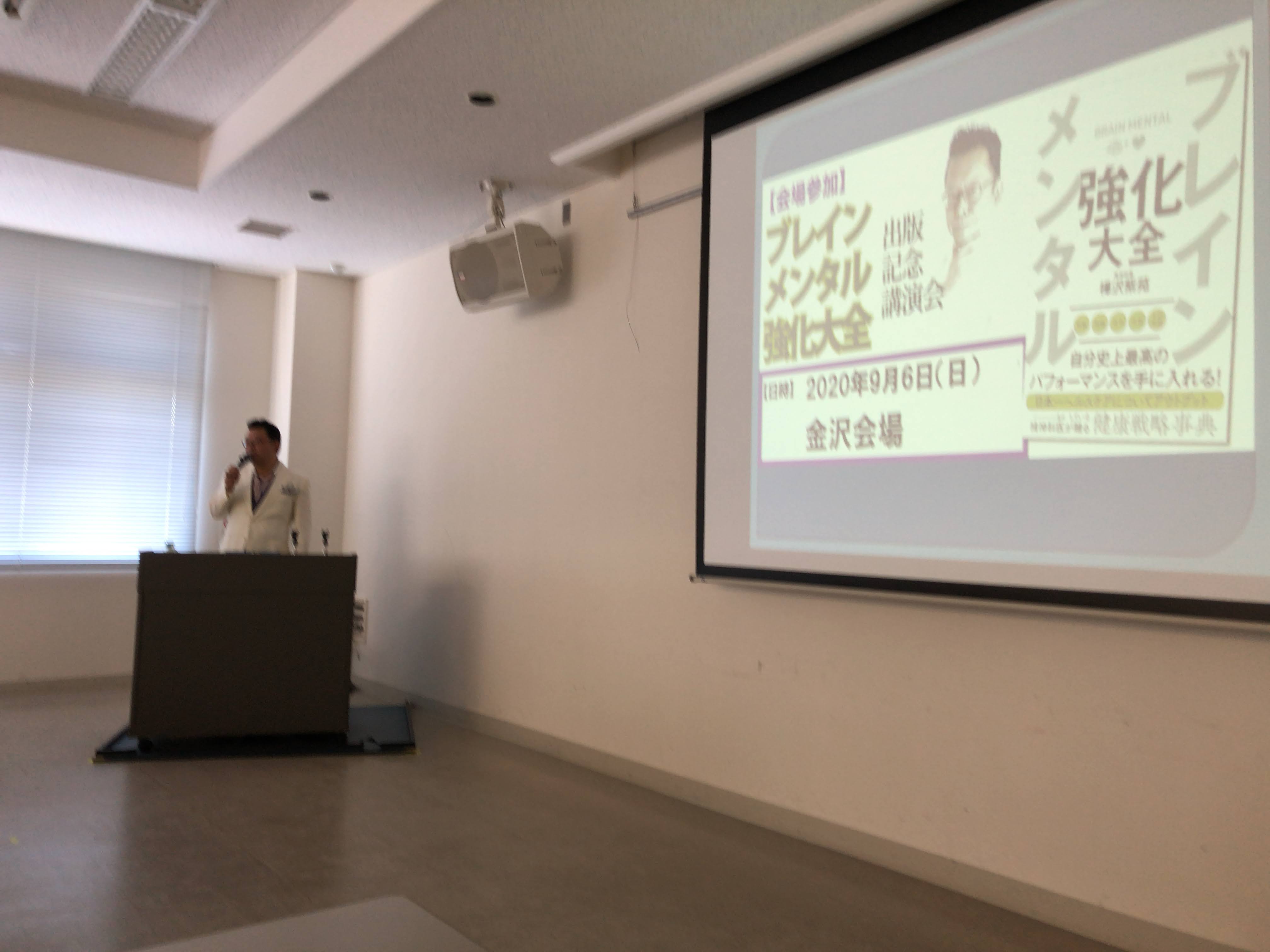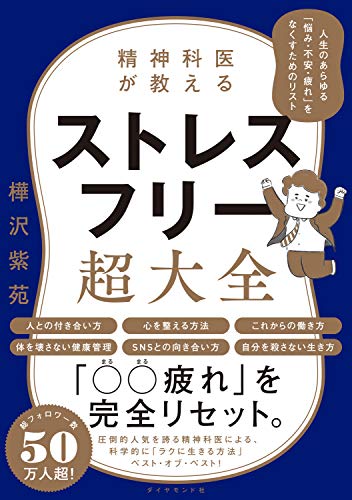石川県金沢市の労働弁護士徳田隆裕のブログです。
未払残業・労災・解雇などの労働事件を中心に,
法律問題を分かりやすく解説します。
労働者の方々に役立つ情報を発信していきますので,
よろしくお願いします。
未払残業代請求事件において管理監督者の判断は厳格にされます
1 管理監督者とは
現在、私が担当している未払残業代請求事件において、
会社から、私のクライアントは管理監督者なので、
残業代を支払わくても違法ではない、という主張がされています。
労働者に、支配人、マネージャー、店長などの役職が与えられていて、
残業代が支払われていないケースでは、必ずといってもいいくらい、
会社からは、管理監督者の主張がでてきます。
それでは、単に役職がつくだけで、管理監督者に該当するのでしょうか。

結論としては、管理監督者に該当するかについては、
厳格に判断されるので、単に役職がつくだけでは、
管理監督者に該当しません。
労働基準法41条2号の管理監督者に該当すれば、
残業代について規定されてる労働基準法37条が適用されなくなるので、
管理監督者には残業代が支払われなくてもよいことになるのです。
もっとも、労働基準法の原則は、1日8時間労働であり、
これを超えて働かせた場合には、
会社に残業代を支払わせることを義務付けして、
長時間労働を抑止しようとしているのです。
管理監督者は、この労働基準法の原則の適用が全て排除されるという、
重大な例外なので、管理監督者に該当するかについては、
厳格に判断されるのです。
管理監督者の範囲は厳格に画されるべきと判断した裁判例として、
HSBCサービシーズ・ジャパン・リミテッド(賃金等請求)事件の
東京地裁平成23年12月27日判決
(労働判例1044号5頁)があります。
2 管理監督者についての3つの判断要素
管理監督者に該当するかについては、厳格に判断されるところ、
次の3つの点が判断要素とされています。
①経営方針の決定への参加ないしは、
労働条件の決定その他労務管理について
経営者との一体性をもっているか(経営者との一体性)
②自己の勤務時間に対する自由裁量を有するか(労働時間の裁量性)
③その地位にふさわしい処遇を受けているか(賃金等の処遇)
①については、会社の経営にどの程度関与していたのか、
採用・解雇・人事考課といった人事権を与えられていたのか、
現場業務も担当していてかなどが考慮されます。
会社の経営会議には参加していない、
アルバイトの面接はするものの、採用の決定権限はない、
マネージャー業務以外の現場業務を多く担当している、
といった場合には、管理監督者ではないことになります。
②については、タイムカード等による出退勤管理がされていたり、
仕事が忙しくて出退勤の自由がない場合には、
管理監督者ではないことになります。
③については、給料や賞与がその地位にふさわしい
水準になっているかを検討することになります。

管理監督者といいながら、2~3万円の管理職手当が
ついてるだけでしたら、管理監督者ではないことになります。
また、賃金センサスという、日本人の平均的な年収の統計や、
業界の平均的な年収と比較して、当該労働者の待遇が低かったり、
平均と同じくらいですと、管理監督者ではないことになります。
業界の平均的な年収については、
ネットで検索すれば、すぐにみつかります。
管理監督者というわりには、給料が低い場合には、
だいたい管理監督者は否定されます。
以上みてきたように、管理監督者については、
上記の3つの判断要素をもとに厳格に判断していきますので、
管理監督者に該当することは少ないと考えますので、
役職がついていても、未払残業代をあきらめる必要はないのです。
本日もお読みいただきありがとうございます。